|
・厳寒の中、唐突な衆議院選挙である。高市首相は私を選ぶかどうかの信任選挙だといった。意味が分からないが、選挙情勢では自民単独過半数の勢いだと言う。本当の解散理由は何なのか。統一教会の問題が韓国で裁判になっていて、その資料が公開された。そこには安部や萩生田をはじめ自民党議員の名前が数多く登場し、高市の名もあると言う。国会で追求されたらとんでもないことになるのは明らかだった。あるいは維新の国保逃れの問題もあって、身を切るどころか身を肥やすことに腐心していたのだから、これも問題にされたくなかった。などなど、国会を開いたらやばいと思われることが目白押しだったのである。 ・来年度予算が可決し、国会が終わってからの選挙と言われていたが、それでは高市人気は下落して、選挙ではとても勝てなくなってしまう。首相にはそんな危機感があったのではと言われている。実際選挙に入ると、統一教会も国保も、あまり話題にならなくなった。で、公明と立憲が合体して「中道改革連合」になったとは言え、高市政権は安泰だろうと言うのが、大方の選挙情勢である。高市首相は信任されたら国論を二分するような政策を行うから、その白紙委任が欲しいと言っている。その中身については何も語らないから危ないことこの上ないが、それでもいいと思っている人が多いのだから、こんな恐ろしい選挙はないだろうと思う。 ・国論を二分するような政策とは何なのか。それはたとえば非核三原則の改訂で核兵器を所有できるようにするのではと言われている。それを使うためには原子力潜水艦が必要だが、その建造も狙っているのかもしれない。それらを含めて防衛費をGDPの2%ではなく3.5%に増額し、さらにアメリカの言うがままに5%にもすることまでやろうと思っているのだろうか。そのための予算は税金や国債に頼るのだが、日本の経済は破綻してしまうにちがいない。彼女の言う積極財政は安部政権時の経済政策で失敗が明らかなアベノミクスの焼き直しにすぎないのである。 ・ベネズエラの大統領を拉致しグリーンランドをよこせと息巻いているトランプ米大統領は、中国に対しては極めて弱腰だ。西半球の支配は譲れないが東は勝手にやってくれ。そんなことを言い始めている。つまり台湾有事にアメリカ軍が出る可能性はないと言っているわけで、日本はどうするんだと聞きたくなってしまう。高市はこれまで以上にアメリカに言いなりだから、単独でも行けと言われれば戦いを挑むなんてことをやるかもしれない。 ・高市人気を支えているのは若者層のようだ。初めての女首相、はっきりものを言って勇ましいし、見栄えもいい。そんな声が聞こえるが、日本の将来を担う人たちには高市政権の本質が見えていないのだろうか。自衛隊は人手不足だから徴兵制をなんて言われたら若者たちはどういう反応をするのだろうか。老い先短い僕にとってはどうでもいいことだが、何ともおぞましい未来しか思い浮かばない。 ・それにしても、前回は排除された壺議員や裏金議員がすべて公認された。代わりに石破に近い議員が冷遇されている。何とも露骨なやり方だが、自民党の穏健派が選挙後に大挙して離党なんてことはおこらないのだろうか。一縷の望みを夢想したくなった。 |
2026年2月2日月曜日
厳寒のお粗末選挙にうんざりだ!
2025年8月25日月曜日
メディアに対する疑問、不安、そして怒り
|
・参議院選挙後すぐに、「石破退陣」という見出しがいくつもの新聞に躍った。読売は号外も出したのだが、石破首相はいまだに辞めていない。しかもどの新聞社も「退陣」が誤報だったと認めていない。いったいどういうつもりなのだろう。その新聞が、石破首相の続投を望む声が高くなっていることを世論調査で発表している。退陣報道が一種の世論操作だったとすれば、それが全く効果なしだったわけで、今さらながらに新聞の影響力のなさを実感した。 ・その参議院選挙で「参政党」が大躍進した。「日本人ファースト」というスローガンが功を奏したと言われているが、それは選挙活動をSNSで配信して、多くの人に浸透させる戦略の勝利だとも言われている。選挙でネットが強力な武器になることは兵庫県の知事選や都知事選、そして都議選でも明らかだったが、今回もまたそれが立証されたのである。その「参政党」の政策について新聞は強い批判を浴びせているが、それで支持率が下がったわけではない。これもまた新聞の影響力のなさを証明するものである。 ・新聞の発行部数はどこも大きく減っている。特に若い世代には読まれないから、ますます影響力をなくすのは明らかだろう。僕は毎朝読むことを半ば習慣のようにしているから、まだ止めようとは思っていなかったが、「退陣」の誤報とそれを謝罪しない姿勢には呆れて、もう止めようかという気になっている。嘘偽りが平気で拡散するネットがますます強力になっているのだから、新聞にはもっとがんばってほしいという気もあるのだが、頼りないことこの上ないのである。 ・もっともネットには、知りたいことを検索すれば、その情報が豊富に蓄積されているといった一面もある。たとえば大阪万博では会場の設営に当たった業者にその代金が払われていないといったケースが多発している。それを伝えて問題視するのはフリーのジャーナリストが多く、また当事者が直接発する声が載っていたりする。現在わかっているだけで7つの国の会場に関わった19社で、中には億単位の被害にあっていて、倒産の危機にあるところもあるようだ。ところが多くの新聞は、この問題を小さくしか扱っていない。 ・万博批判に消極的なのは今に始まったことではない。これは新聞社自体が協賛していたり、関連の広告収入があるためだと言われている。地下鉄の故障で万博会場や駅に足止めになって夜明かしをした人が3万にもいたそうだ。ものすごい数で、猛暑の中体調を崩した人も多くいただろうと思う。これもネットには、足止めされた本人の書き込みなどが溢れたのだが、新聞の報道はごく小さなものだった。 ・新聞はジャーナリズムを代表する機関で、社会を正確に映しだす鏡であるべきだと言われてきた。しかしその影響力が弱まった今、新聞にとって重要なのは企業として生き残るための方策なのである。もっともこの点でもっと露骨なのはテレビだが、このメディア、とりわけ民放についてはもう見限っていて、批判する気さえなくなっている。ネットのSNSには両刃の剣といった特徴がある。匿名だから何を言ってもいい。騒ぎが大きくなるならどんな手段を使ってもいい。そんな傾向が野放しになっている。これもネットを支配する企業が利益優先の方針であるからで、規制する策をほどこさなければますますひどくなるばかりだと思う。 |
2025年6月2日月曜日
『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』
 ・トランプ大統領の傲慢なやり方に世界中が振り回されている。強欲で過信家で人を平気で差別する。そんな最低の男がなぜ大統領に二度もなれたのか。この映画を見て、そのことがよくわかった気になった。
・トランプ大統領の傲慢なやり方に世界中が振り回されている。強欲で過信家で人を平気で差別する。そんな最低の男がなぜ大統領に二度もなれたのか。この映画を見て、そのことがよくわかった気になった。・原題は"THe Apprentice"で「徒弟」とか「見習い」といった意味である。父親の仕事を継いで不動産業を始めたばかりのトランプは、気弱で優しさのある青年だった。その彼が悪名高い弁護士と出会い、徹底的に鍛えられて、現在のような性格の人間になっていく。題名にはその見習いから成り上がる過程の意味が込められている。しかし、不動産業やカジノで成功したトランプには、テレビ番組の司会役として人気を博したという一面もあって、その番組名も「アプレンティス」だった。 ・トランプが従順に従う弁護士のロイ・コーンはソ連のスパイとして告発され、死刑にされたローゼンバーグ夫妻の裁判で検事を務め、赤狩りで有名なマッカーシーの主任顧問もした人物である。その後もニクソンやレーガンといった共和党の大統領にも取り入って、政界や財界で絶大な権力を誇ったが、トランプが出会った頃は、コーンの絶頂期であった。 ・映画ではコーンの教えに素直に従い、苦境を強引な手法で乗り超えてホテルやトランプタワー、そしてアトランティック・シティにカジノを造って成り上がっていく様子が描かれる。対照的に同性愛者であったコーンが体調を崩すと、トランプはコーンを遠ざけ、やがてさげすむようになる。最後はコーンの誕生日にパーティを開き、ダイヤモンドのカフスボタンをプレゼントするが、それが偽物であることが暗示される。恩をあだで返す卑劣な男だが、この映画はトランプの薄くなった頭の増毛と、腹に溜まった脂肪の除去手術で終わるのである ・トランプが大統領選挙に登場する前の経歴についてはほとんど知らなかった。しかし、ウィキペディアなどによれば、映画の後の人生は、決して順風満帆ではなかったようである。彼は1980年代にはホテルやカジノで成功したものの、その多くが90年代になると倒産して巨額な負債を抱え込んでいる。映画にも登場する最初の結婚相手のイヴァナとは浮気が元で離婚をしているし、その浮気相手との再婚も、数年で浮気が元で離婚をしている。 ・しかしトランプは90年代の後半には不動産業で持ち直し、2004年から12年まで続いたテレビ番組の「アプレンティス」によって、全米に知られる有名人になった。大統領選挙に最初に勝ったのは2016年だが、選挙には2000年の予備選挙にも出ていたし、2012年には共和党の候補にもなった。最初は泡沫候補扱いで、繰り返される暴言に多くのメディアが反撥したにもかかわらず、共和党の予備選で勝って候補者になり、おおかたの予想を覆して、ヒラリー・クリントンに勝って大統領になった。で、バイデンに負けた後も屈せず再度挑戦して復活した。 ・彼は、人としては軽蔑するしかないような人間に思える。しかしその不屈の精神と復活の実現には、アメリカン・ドリームを体現する人物として人気を得るのも無理はないとも感じられる。そんな根性をたたき上げたのがロイ・コーンだとすれば、彼が亡霊としてトランプを操っているのではといった想像をしたくなった。いろいろ調べてみると、若い頃のトランプは、むしろリベラルな考え方をする青年だったとする指摘が見られるのである。 |
2025年5月26日月曜日
観光客はありがた迷惑です
 ・河口湖に来る観光客がすごいことになっています。週末の混雑はずいぶん前からですが、最近は平日でも変わりません。おかげでゴールデン・ウィークの間は、どこにも出かけずに家に閉じこもることになりました。例年なら3月になったら、午後に自転車で湖畔を1周していたのですが、暖かくなる午後ではクルマも人もレンタル自転車もいっぱいで、とても出かける気にはなりませんでした。連休明けから、観光客がまだ動き出していない早朝に自転車に乗りはじめています。しかし、通勤のクルマがかなりあって、気をつけて走らなければなりません。何しろ河口湖周辺は宿泊施設や食べ物屋などが増えて、周辺から仕事に通ってくる人が多いのです。 ・河口湖に来る観光客がすごいことになっています。週末の混雑はずいぶん前からですが、最近は平日でも変わりません。おかげでゴールデン・ウィークの間は、どこにも出かけずに家に閉じこもることになりました。例年なら3月になったら、午後に自転車で湖畔を1周していたのですが、暖かくなる午後ではクルマも人もレンタル自転車もいっぱいで、とても出かける気にはなりませんでした。連休明けから、観光客がまだ動き出していない早朝に自転車に乗りはじめています。しかし、通勤のクルマがかなりあって、気をつけて走らなければなりません。何しろ河口湖周辺は宿泊施設や食べ物屋などが増えて、周辺から仕事に通ってくる人が多いのです。・その宿泊施設ですが、ネットで調べると、どこも数年前の1.5倍から2倍、あるいはそれ以上の料金になっています。家の近くにあるペンションは、修学旅行生を受け入れて何とかやっていたようですが、料金を倍にしても、予約が取りにくいほどににぎわっています。コロナ禍で患者の収容施設になっていた有名なビジネスホテルも、今ではけっこうな料金になっています。部屋に温泉があったり、豪華な食事を出すホテルは1泊2名で6万円とか7万円もしていますが、それでも予約が取りにくいようです。 ・高額になっているのはインボイスのせいで、河口湖に限らないようです。円安ですから倍になったからと言って、外国人は高いと思わないのかも知れません。それも欧米からの人に限らず、アジアからの人にとっても同様のようです。お金に余裕のない日本人の客はどこに泊まるんだろうと思いますが、貨物列車を改造した宿泊施設もあちこちに出来ていて、ここなら1泊2名で食事付きでも1万5千円程度で泊まれます。ここ数年はキャンプブームでもありますが、隣の西湖には平日からかなり多くの人がキャンプ場に訪れています。コロナ前なら自転車で走っても、クルマも人もほとんどいなかったのですが、今ではそうではありません。 ・このような現象は町にとってはいいことだと思います。何しろ人口減に悩む山梨県の中で、例外的に人口が増えているのです。町内には宿泊施設が700軒ほどあり、年間200万人を超える宿泊者数があるとされています。この急激な増加に対応して再来年から宿泊税を取ることにしたようです。富士登山をする人には昨年から2000円の入山料を取りはじめています。今年は静岡県も実施して、4000円に値上げされました。ただし、町に入る収入が町民に還元されているとは実感できません。感じるのは迷惑ばかりですから、コロナ禍の頃の閑散とした様子が懐かしく思われます。 ・隣町の富士吉田市は人口減に悩まされています。河口湖町と違って観光名所もなかったので、素通りされる町でしかなかったのですが、山の上の五重の塔と満開の桜越しに見える富士山がネットで紹介されると、急に観光客が集まるようになりました。商店街の真ん中に富士山が見えることで、シャッター通りに外人観光客がひしめくようにもなりました。かつては富士山の登り口で、御師(おし)の宿もたくさんあったのですが、5合目までのスバルラインが作られてからは、吉田口の登山道は閑古鳥状態でした。しかし浅間神社からの登山道を魅力的にする工夫なども計画されているようです。 ・梅雨の先触れのような天気でも、河口湖では湖越しに、あるいはコンビニの上の富士山を眺める場所に観光客が溢れています。これから夏にかけては富士山が雲に隠れる日が多いのですが、それでも人が減るわけではありません。そんな光景を見て「残念でした!」と口ずさみたくなるのは、意地悪爺さんの性でしょうか。 |
2025年5月19日月曜日
米の値段について
|
・米の値段が倍以上になった。その急激な値上がりは信じられないほどだが、政府が備蓄米を放出しても効き目はないようだ。なぜこうなったのか。一番の理由は昨年の夏に米の供給量がひっ迫して値段が上がり始めた時に、政府が素早く対応して備蓄米を放出しなかったことだろう。新米が出回りはじめれば価格は落ち着く。そんな見通しだったのかも知れないが、価格はさがるどころかどんどん上がってしまい、政府が備蓄米の放出を決めたのは、今年の2月になってからだった。 ・この時点ですでに半年遅れだが、その備蓄米が市場にほとんど出回らないことで、価格はさらに上がり続けている。理由は流通経路に隘路があることや、備蓄米さえ買いだめしている業者がいるといった疑念が指摘されているが、備蓄米を買えば1年以内に政府に戻すことが義務づけられていることが一番だったようだ。そこで政府は1年ではなく5年にすると発表した。さてこれで、備蓄米が大量に出回って、価格が値下がりするのだろうか。 ・政府や農水省の対応の悪さに呆れるばかりだが、米は今の価格でも高くはないといった発言も聞こえてくる。米を作ってもそれ相当に収入が得られるわけではない。そんな農民の声が多く聞かれるからだ。米の消費量はずっと減り続け、それに対応して減反政策が採られて来たのだが、田を畑に代えることはそう簡単ではなかったようだ。 ・農業従事者の多くは他に仕事を持つ兼業農家が大半だから、収入が得られなければやめるだろうし、高齢化で引退といった人たちも増えてきている。何しろ農業従事者の平均年齢は70歳に近づいていて、65歳以上が70%という現状になっているのである。それ相当の収入が得られなければ、若い人の中に農業をやろうという気持ちが起こらないのは当然のことなのである。 ・僕の家の周辺にも田畑はたくさんある。しかし、田んぼがブルーベリーやサクランボ、あるいはワイン用の葡萄畑などに変わり、草ぼうぼうの放棄地になったところも少なくない。農業の衰退は周囲の様子を見ればすぐ分かることである。 ・最近の物価の値上がりは米に限らないが、急に倍以上になるというのは異常という他ないだろう。それは価格をずっと抑えてきた政府の農業政策にこそ問題があったのかもしれない。その意味では、現在の米価を適正なものとして、それを農家の収入の上昇に向けることが懸命だと言えるだろう。育ち盛りの子どもがいて大変な家庭もあるだろうが、それは食料品にかかる消費税を廃止したり、低所得者への減税や補助などで対応すべきことだと思う。 ・もちろん、それで若い人の中に農業をやってみようという意欲がわくわけではないだろう。しかし日本の食料自給率は4割を切り、飼料の自給率は3割を切って、化学肥料はほぼ100%輸入に頼っているのである。最近の国際情勢や気候変動などを考えれば、自給率を高めることが喫緊の課題であることは明らかなはずだ。農業従事者の大半が定年退職の時期にさしかかっている現状を見るにつけ、日本の食の現状と近未来こそが、一番の危機なのではと心配してしまう。 |
2025年4月28日月曜日
あまりにお粗末な万博について
|
・大阪万博には全く興味がない。もちろん行く気もないのだが、あまりにひどいニュースばかりが耳にはいるから、ここでも取り上げておこうと思った。そもそも大阪万博は夢州にカジノを含んだ統合型リゾート(IR)を作るためのインフラ整備として計画されたと言われている。実際、半年の開催だけのために地下鉄が延伸されたのだが、これがIR用であることは自明のことだった。夢州はゴミで埋め立てられた土地で、まだ地盤が固まっていないし、メタンガスなども出る。輸入品が入るコンテナヤードにもなっていて、ヒアリなども確認されている。そんな危ない場所が適地であるはずがないのは最初からわかっていたことだった。 ・万博会場は開催直前にも危険なレベルでメタンガスが出ていることがニュースになった。それを調べたのは万博開催者ではなく、共産党の市議だった。そのせいか万博協会はメディアの中で唯一共産党の機関誌である赤旗の取材を拒否した。万博についてはこれまでも多くの批判があったが、その多くは大手メディアではなく、赤旗などの小さなメディアやフリーのジャーナリストによる告発だった。新聞やテレビなどの大手メディアの多くは万博開催に協賛していて、その恩恵に浴しているから、批判は少なく、広報としての役割を演じる場合が多かったのである。 ・大阪万博のいい加減さ、怪しさについては主にフリーのジャーナリストによって、YouTubeやSNS、あるいはブログなどによって指摘され、批判されてきた。最初はなかった木造の大屋根リングについては、その費用の巨額さ、業者選定の不透明さなどがあるが、万博協会はこの批判に対して知らん顔を決め込んでいる。そんな態度は他の指摘でも同様で、各国のパビリオンの建築が遅れて開催に間に合わなかったことや、前売り券の売り上げが伸び悩んでいることなどについても、謝罪はもちろん、弁明もほとんどない。 ・そんな問題ばかりの万博が開催されたが、初日はものすごい風雨で、訪れた人たちは入り口で何時間も待たされてずぶぬれになった。大屋根リングも雨宿りの役には立たなかったようである。最近の天気は気まぐれで、好天になれば夏のような暑さになる。その熱中症対策なども貧弱で、ネット上では雨が降っても晴れても問題が起きるお粗末さばかりが話題になっている。対照的にテレビや新聞では、万博の魅力を宣伝しているのだが、行きたい気にさせる呼び物がほとんどないのだから、虚しい限りである。 ・万博の収支分岐点は1800万人の入場者数に達するかどうかだと言われている。ところが前売りはその半分にも達していない。しかもその大半は協賛者である企業に半ば強制的に買わせたもので、一般の購入は200万枚程度にしかなっていない。これは最初目標にした1400万枚の65%程度でしかなく、今後の当日券で入る入場者数を考えても、赤字になるのは明らかだろうと言われている。ところが万博協会は想定内で、今後の伸びに期待するなどと言っているのである。 ・そもそも万博は、海外旅行が当たり前になり、ネットが発達した現在には、もう役目を終えたイベントなのである。どこかの国に興味があれば、そこに出かければいいし、ネットで検索すればかなりのことが瞬時にわかるのである。また大阪万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにしているが、一体どこに未来のテーマが提案されているのか。空飛ぶ自動車は見掛け倒しだし、人間洗たく機などは冗談としか言いようがない代物である。広い会場は歩いてまわらなければならないし、トイレは汲み取り式で小児用には仕切りもない。近未来と言うなら、歩かなくても見て回れる手段が工夫されてもよかったはずである。 ・これから猛暑になれば熱中症者が続発するかもしれないし、メタンガスが爆発するかも知れない。雷が来ても逃げ場がないなど、いいことがほとんどないイベントは、大赤字を出して閉幕といったことになるのだと思う。そうなった時に一体誰が責任を取るのか。おそらく最後まで知らん顔を貫くはずで、そんな近未来のデザインが目に浮かぶだけである。 |
2025年4月14日月曜日
広告は神話にすぎないのでは?
|
・YouTubeのCMがひどいことになっている。何を見ても3分と経たずに中断されるから、邪魔なことこの上ない。中にはスキップできないものがあるし、ほっておくと続けて次々やったり、やたら長かったりする。フジテレビが広告なしになった分だけ増えているのかも知れない。えらい迷惑で、腹が立つばかりなのに、それでも宣伝したら効果があると思っているのだろうか。 ・前回も書いたが、フジテレビにCMを流さなくなった企業の売り上げに変化が出たのだろうか、が気になっている。もし変化なしだったら広告費は無駄だったということになる。そんなデータがいくつも出てきたら、テレビに広告費を使う企業は減るに違いない。テレビに広告費を使えば、それなりに大きな効果がある。というのはもはや神話に過ぎないのでは、という感想を僕はずいぶん前から持っていた。 ・民間放送を広告費で成立させたのはアメリカのラジオ放送だった。20世紀になって音を遠くに届ける方法が有線と無線の両方でできた時に、使用料が取れる有線を電話にし、広告費で稼げる無線をラジオにしたのは有名な話である。有線と無線を電話とラジオに使い分けることに技術的な理由はなかったのである。そのやり方はテレビ放送にも継続されたが、その歴史はまた、家電製品や自動車から日常生活に必要なさまざまな製品が発売され、普及した時代でもあった。 ・もちろん、それらは今でも日々消費されたり、買い替えられたりしているが、消費行動がCMを当てにする割合が減っていることも間違いない。ネットには様々な商品や製品を比較するサイトがいくつもあるし、Amazonや楽天で性能や値段を比較して、自分なりに判断することもできる。それにかつてはテレビCMの主流だった家電製品の多くを日本のメーカーは生産しなくなっているし、作っていたとしても、広告費を使って安価な外国製品と競ってはいない。テレビ受像機や冷蔵庫などの家電製品のCMは、実際ほとんどなくなっているのである。 ・そう言えば、トランプの関税政策で日本のメディアは大騒ぎだが、大きな影響を受けるのが自動車だけだということに、日本の経済力の衰退を改めて認識させられた。かつてはアメリカの家庭の中に溢れていたメイド・イン・ジャパンの製品は、今は関税を心配するほど売れていないのである。これでは貿易額が輸入超過になるわけである。だから、クルマが売れなくなったら、日本の経済は本当に沈没してしまう。それだけ深刻な話のようである。 ・で、YouTubeのCMだが、見ているものを中断するのはほぼ100%関心がなかったり、よくわからないものばかりである。だから音楽を聴いたり、野球の結果を見ている時に邪魔されると腹が立つだけなのだが、それでも何らかの効果があるとする根拠があるのだろうか。もちろん、僕は老人だから、もっと若い人には効果があるといったこともあるかも知れない。だとしたら、視聴している人の好みや年齢などに合わせてCMを届けるぐらいのことは、やろうと思えばできるのではないだろうか。今は何しろAIの時代でアルゴリズムが全盛になりつつあるのである。もっとも、今一番興味があることやこれから買おうと思っていることを見透かされたら、それはそれでちょっと困るし、怖くも感じてしまう。 ・ついでにいえば、電波の利用はその経済的な理由で無線がマスメディアになり、有線がパーソナルメディアになったが、100年経って完全に逆転したのも面白い結果である。電話はスマホが主流になり、インターネットは有線として発展したのである。もちろんスマホは無線でインターネットを利用しているから、無線も有線もインターネットが支配するようになるのは自明だろう。テレビによる電波の独占は、もはや時代錯誤なのである。 |
2025年4月7日月曜日
MLBが始まった!
|
・MLBが始まって、今年もテレビ観戦が一日の中心になりました。きこりや大工仕事が終わったところで切りがいいのですが、運動不足になりますから、自転車にも乗ろうと思っています。ところがここのところ雨ばかりで、まだ一度も走っていません。観光客でにぎやかですから早朝になるでしょう。 ・今年もドジャースはアジアでの開幕で、東京ドームはにぎやかでした。何しろカブスが相手で、大谷、山本、佐々木に今永、鈴木と、日本人選手が5人も勢ぞろいしたのです。阪神や巨人との試合も含めて超満員で、テレビ視聴率も驚くほどでしたから、MLBは日本での開催を常態化するかも知れません。と言っても来年はWBCですから、春の盛り上がりはまた別のものになるでしょう。 ・ワールドシリーズを制覇したドジャースは、オフにさらに戦力をアップさせました。攻守にわたってもう穴がないほどで、力があってもマイナーで我慢しなければならない選手が大勢います。その力は予想通りで、ドジャースは開幕から8連勝し、どの試合も危なげなく勝ってきました。強すぎて面白くないといった声も聞こえますが、唯一、佐々木朗希投手が気になっていました。 ・東京ドームではいきなり100マイルの球を投げて、観客席からどよめきが起こりましたが、明らかに力みすぎで、ストライクが入らずに降板しました。ドジャー・スタジアムでの2戦目はもっとひどくて、全くストライクが入らず、早々降板した後に、涙目をして散々批判されました。フィラデルフィアでの3戦目も初回に1点取られましたが、制球力はあって、何とか四回まで投げることができました。強敵のフィリーズ相手に試合を作ったのですから、自信になったことだろうと思います。 ・今年は日本人投手の存在が目立ちます。山本投手はプレイオフでの力を持続していますし、今永投手も安定したピッチングをしています。エンジェルスに移った菊地投手はエースですし、メッツの千賀投手もカムバックできそうです。30代の半ばになってメジャーに挑戦した菅野投手はその制球力のよさが目立っています。大谷選手の復帰がいつになるのかわかりませんし、ダルビッシュ投手も故障していますが、全員そろったら壮観だと思います。 ・東京での開催の大成功や日本人選手の活躍で、メジャーリーグでの日本の位置づけが上がっています。何しろ大谷選手はメジャーで一番の成績を上げているだけでなく、広告収入や観客動員でドジャースはもちろん、他チームやMLB機構に恩恵をもたらしているのです。もちろん大谷選手の収入は飛び抜けていて、野球だけでなく他のプロスポーツ選手と比べても、トップに君臨するほどなのです。 ・トランプ大統領の関税政策で世界中が大混乱ですが、クルマの輸出に依存している日本経済の先行きも危ぶまれています。よい話がまるでないなかで、大谷選手を始めとしたメジャーで活躍する選手が目立っています。テレビでは一日中話題にされていますし、ニュース番組でも大谷一辺倒です。それに民放での大谷選手のCMですから、これは大谷ハラスメントだといった批判が起こるのも無理はないでしょう。野球に興味のない人には腹立たしいことだと思います。MLBで日本人選手が活躍すればするほど、日本のダメさ加減が目立ってしまう。そんな皮肉な印象を持ってしまう今日この頃です。 |
2025年3月24日月曜日
吉見俊哉『東京裏返し』集英社新書
|
・東京には10代の頃に住んでいたし、50歳から20年近く大学勤めをした。ただし家も職場も多摩地区にあったから都心に出かけることはめったになかった。息子家族が下町に住むようになって時々出かけたが、都心はいつもクルマで首都高速を走るだけだった。人混みばかりのコンクリートジャングルには行く気もしない。東京の中心部については今でもそんな気持ちが強い。 ・吉見俊哉『東京裏返し』は東京の都心部を歩いて観察し、その現状を批判的に分析している。主に都心の北部を歩いた「社会学的街歩きガイド」と西部から南部にかけて歩いた「都心・再開発編」の2冊にまとめられているが、知らないことばかりで面白かった。 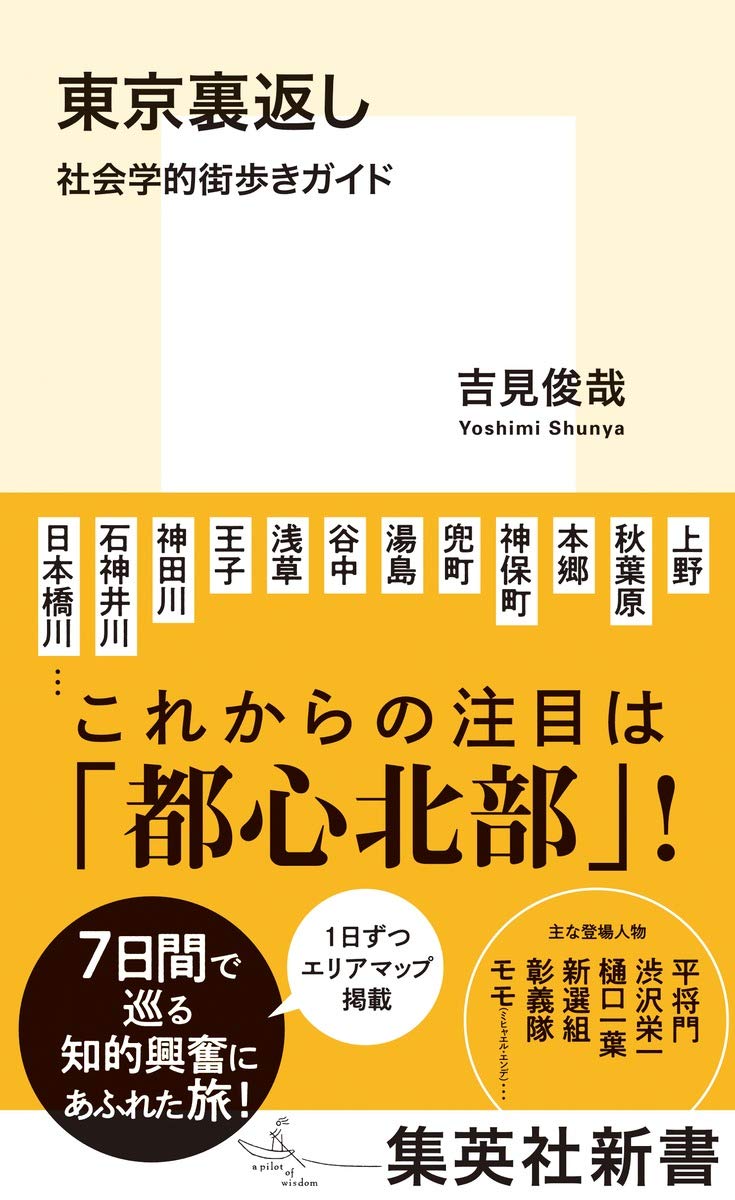 ・東京についてこの本で提示されている視点は、東京が3度侵略され、その度に大きく変容したということである。最初は徳川家康による江戸、2度目が大政奉還と明治維新による東京、そして3度目が大戦に負けて米進駐軍による統治と戦後の復興である。もちろん東京には縄文時代から人々が住んでいて、貝塚や古墳も見つかっている。
・東京についてこの本で提示されている視点は、東京が3度侵略され、その度に大きく変容したということである。最初は徳川家康による江戸、2度目が大政奉還と明治維新による東京、そして3度目が大戦に負けて米進駐軍による統治と戦後の復興である。もちろん東京には縄文時代から人々が住んでいて、貝塚や古墳も見つかっている。・その点については中沢新一の『アースダイバー』で教えられた。東京は武蔵野台地の東端にあって、半島のようにつきだした台地と谷筋を流れる川ででき上がっている。縄文海進で海は今よりもずっと西まであったし、江戸時代には埋め立てをして、土地を広げている。『東京裏返し』でも、この地形の重要さを指摘していて、尾根筋から谷筋、あるいはその逆を下ったり上がったりしながら歩いている。 ・徳川幕府は200年続いて、その間に江戸は世界有数の大都市になった。今でもその名残は強くあるが、この本では、明治政府によって徳川の痕跡がことごとく消されたことが示されている。その特徴的な場所が現在の上野公園周辺で、寛永寺などに象徴的に見られると言う。また明治政府はその政治や経済の中心を南に移したから、北部は取り残されることになって、下町地情緒が現在も消えずにある。 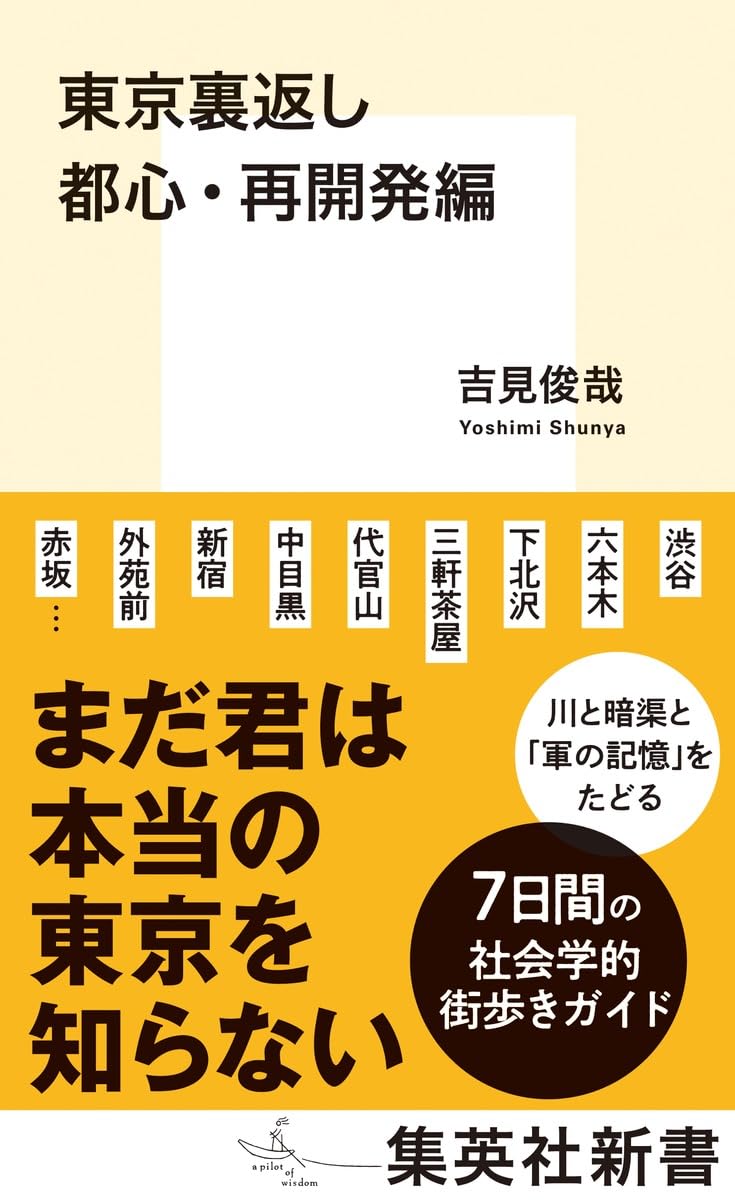 ・「都心・再開発編」で歩いているのは下北沢から渋谷、そして麻布、四谷、新宿などである。ここでは明治時代からあった軍の施設とそれが進駐軍によって接収された影響と、戦後の西武や東急による土地買収と、ビルや住宅地への変貌ぶりが批判的に指摘されている。江戸時代の大名屋敷や戦後に困窮して手放した皇室所有の土地が何に変わったか、谷筋にあった庶民の暮らしが、どう潰されていったか。東京の現状が、歴史を残すことなど無頓着に、経済優先のやり方で進められていったかがよくわかる街歩きになっている。そのような流れは今も、そしてこれからも変わらずに続けられていて、その象徴を六本木や麻布に立てられた高層の森ビルなどに見ている。
・「都心・再開発編」で歩いているのは下北沢から渋谷、そして麻布、四谷、新宿などである。ここでは明治時代からあった軍の施設とそれが進駐軍によって接収された影響と、戦後の西武や東急による土地買収と、ビルや住宅地への変貌ぶりが批判的に指摘されている。江戸時代の大名屋敷や戦後に困窮して手放した皇室所有の土地が何に変わったか、谷筋にあった庶民の暮らしが、どう潰されていったか。東京の現状が、歴史を残すことなど無頓着に、経済優先のやり方で進められていったかがよくわかる街歩きになっている。そのような流れは今も、そしてこれからも変わらずに続けられていて、その象徴を六本木や麻布に立てられた高層の森ビルなどに見ている。・この本には著者による東京改造の構想も書かれていて、その一つは一路線に減らされた都電の復活である。東京オリンピックを契機にして、東京は高速道路と地下鉄の街に変容した。その首都高を撤去し、トラムカーの路線を増やし、歩いて、あるいは自転車に乗って探索できる街にしようという提案である。実際ヨーロッパでは都心部へのクルマの乗り入れを禁止して、路面電車を復活させた街が多いのである。 ・もう一点は縄文時代から続く東京の歴史について、とりわけ江戸から現在に至る遺跡をもっと大事にすべきだという指摘である。僕はこのような提案についてなるほどそうだなと思うところが多かった。日本に訪れる外国人が好むものの中に江戸の香りがあることも確かなようだ。ただし、読んでいて気になるところもあって、それは今よりもっと東京が魅力的になったら、ますます人口が集中して、地方が過疎になってしまうのではという疑問だった。東京はもっとダメな街になったらいいと思っていただけに、ちょっと両義的な気持ちになった。 |
2025年3月17日月曜日
無理が通れば道理が引っ込む
|
・トランプ米大統領の傲慢で横柄な発言が止まらない。輸入品に高額関税をかけることを最大の武器にしているのだが、関税分を負担するのは売り手ではなく買い手だから、払うのはアメリカの消費者自身なのである。トランプの発言に拍手喝采する人は、そのことをわかっているのだろうかと疑問に思う。物価が上がり消費が減って経済が減速するから、当然景気は悪くなる。実際アメリカの株価は急降下していて、それが世界中に影響を及ぼしている。こうなることははじめからわかっているのに、トランプはこれがアメリカ・ファーストの政策なのだと豪語する。まさに無理が通れば道理が引っ込むのである。 ・トランプのやり方はウクライナやパレスチナに対しても変わらない。武器を援助して欲しいならレアアースをよこせと言ったり、ガザからパレスチナ人を追い出して、破壊された町を復興させるといった発言は、大国の大統領が言うとはとても思えないものである。フランスのマクロン大統領が核の傘をアメリカに頼らず、欧州独自で作ると発言している。トランプの発言はプーチンやネタニアフにとっては渡りに船だろう。道理が引っ込んで混乱した世界はどうなるのか。それを回避するために必要なのは、アメリカ国民が事実に気づくことだが、そんな兆候は見られない。 ・無理を通すやり方は日本にも溢れている。一度失職をした兵庫県知事が、不当なやり方で再選し、百条委員会で知事にあるまじき行為を断罪されているのに、それは一つの見方に過ぎないと無視しようとしているのである。この人の悪行は数えきれないほどだが、平気で知事の座に居座り続けている。リコールの請求ができるのは再選から1年を過ぎなければならないから、斎藤知事は少なくとも1年間は安泰なのである。自業自得とは言え、兵庫県民にとっては頭の痛い話だと思う。 ・課税限度額の引き上げを主張した国民民主党が今、立憲民主党を上回る支持を得ている。玉木代表の不倫が発覚しても、その勢いは衰えないようである。その力の源泉は玉木がN党党首の立花に教えを請うて始めたSNSにあるようだ。若い人たちに重い税金が課せられ、老人がその恩恵によくしているといった嘘が信じられて、自民党や維新を支持していた若い人たちがこぞって、国民民主党支持にくら替えしたと言うのである。選挙でSNSをうまく使えば、マスメディアに頼らずとも大量に票を獲得することができる。そんな傾向が都知事選や兵庫県知事選、そして衆議院選挙で明らかになっている。このまま行けば、参議院選挙もSNSが重要な場になってくるだろう。 ・大阪万博が間もなく始まる。前売り券はほとんど売れていないようだし、準備も遅れに遅れているようだ。始まっても閑古鳥といった予測ができるが、ここにも嘘や無理がまかり通り続けてきた。大阪府・市はもちろん国の税金もいっさい使わないと言ったのは、これを始めた松井前知事だが、すでに1000億円以上が投入され、入場者数が少なければ、さらに赤字が増えると見込まれているのである。万博はカジノ目的というのが明らかだが、そのために無理にごみ捨て場に万博を誘致した。ここには最初から道理などなかったのである。 ・世の中には道理を無視した無理が溢れている。それが当たり前になったら、道理など考えるのが阿呆らしくなる。そんな気分が蔓延したら大変だが、もうすぐそこまで来ているような恐ろしさがある。 |
2025年3月3日月曜日
ネットの変貌
|
・ネットの広告費がテレビの倍になった。YouTubeを見ていても数分おきに
CMに邪魔されて不快な思いをさせられているから、確かにそうだろうと思う。
Amazonプライムも4月からCMが入るとメールがあった。金を払っているのにCMなしならさらに金を払えと言う。その露骨な金権主義に象徴されるように、ネットには腹の立つことが目立っている。 ・旧TwitterもFacebookもとっくにやめている。広告が目立つことや、詐欺が横行していること、そして何より所有者がとんでもない大金持ちになっていることに嫌気がさしたからだ。トランプが大統領に復活したら、SNSを所有する多くの人が尾っぽを振って近寄るようになった。それはAmazonの創業者も一緒だった。王様気取りで好き勝手にやっているトランプに、ITやネットもほとんど反旗を翻してはいない。こんな状況に、世の中も変わったものだとあきれ、がっかりしている。 ・国や大企業が独占するコンピュータではなく、個人が使えるものを作るというのは1970年代にアメリカで始まった草の根の動きだった。そこからスティーブ・ジョブズが現れアップルを起業し、パソコンを売りだした。インターネットも同様で、ネット同士を繋げ、そこで使えるソフトを開発することで新しいメディアを作りだした。僕はどちらもその狙いや理想に共感して、初期から利用してきた。パソコンやネットの世界を支配するようになったマイクロソフトに手をつけなかったのも、その商業化に批判的だったからだ。 ・そんな気持ちが通用しなくなったのは皮肉にも、ジョブズが開発したiPhoneの登場だった。ここからネットの世界が大きく変貌しはじめたのである。スマホやタブレットはいつでも手元に置けるし、持ち歩くこともできる。見たいもの聴きたいもの知りたいことに、いつでもアクセすることができるのだから、既存のメデイアがかなうわけはなかったのである。 ・その新しいメディアは今、GAFAと呼ばれる大企業に支配されている。金儲け主義の不動産屋のやり方で世界中を震撼させているトランプを批判するどころか、その政策を支えて、さらに巨大になろうとしている。パーソナル・コンピュータの萌芽期からインターネットの始まりまでを、希望を持って面白がってきた者としては、その変貌には失望と恐怖を感じるしかないのが正直なところだ。SNSだって始まりの頃はもっとほのぼのとしていて、理性的だった。 ・今はその頃に比べてはるかに便利だが、ITもネットもほんのわずかな企業やその支配者に牛耳られていて、それらが政治権力にべったりだ。その便利な道具を使っているのか使わされているのか。それを確かめながら使う程度の自覚は持ちたいと思う。 ・ところで、フジテレビが中居問題でスポンサーが離れて、収入なしで放送を続けている。広告費を使わなくなった企業の、売り上げや収入に変化がなかったとしたら、CMなどしなくてもいいんだと思うようになるだろうか。それはネット広告でも同じで、利用者にとっては邪魔で不快になるものでしかないから、宣伝効果はないとしたらどうだろうか。知名度を高めたり、売り上げを伸ばすためにはメディアでの広告が必要だ。それが真実性に乏しい虚構であることを、誰か実証したらいいのに、とつくづく思う今日この頃である。 |
2025年1月27日月曜日
トランプのゴーマニズム宣言に呆れと恐れ
・トランプが大統領として再登場した。ハリスを圧倒する勝ち方だったせいか、就任前から大気炎を上げる威勢の良さだった。隣国のカナダとメキシコからの輸入を抑えるために関税を25%課す、メキシコ湾をアメリカ湾に変える、グリーンランドをデンマークから買う、そしてパナマ運河を取り返すなどといった発言には、カナダを51番目の州にしたらいいとか、売らなければデンマークにも高関税を課すか武力行使をするといった、相手をバカにしたり威圧したりする態度も見られた。
・こんな強行姿勢に恐れをなしたのか、あるいは側近中の側近になったイーロン・マスクに取り入ろうとするのか、GAFAがそろってトランプ支持を打ち出した。しかも「X」(Twitter)にならってFacebookも第三者によるファクトチェックを廃止したりと、その迎合ぶりはあからさまである。トランプは嘘もお構いなしの発言で支持者を増やすことを得意にしてきたが、SNSの多くがそれを是認しようと言うのである。そういえば大統領選挙期間中にニューヨークタイムズやワシントンポストがそれまでやっていた候補者支持をやめて中立を宣言したのだった。
・選挙に与えるネットの影響が強くなったのは日本でもあきらかで、石丸や立花、そして玉木といった政治家がネットを使って票を伸ばしたり、選挙結果に大きな影響を与えたりしている。特にYouTubeで拡散される立花の言動はひどいものだが、だからといって変な規制をすればかえっておかしなものになる。どうすればいいかはGAFAの態度やそれに対する批判を含めて世界的な課題になるだろう。
・トランプは大統領就任と同時に、バイデンの政策をことごく廃止した。メキシコとの国境を強化して不法入国者を防ぐとか、犯罪歴のある入国者は国外追放するといったことは前の政策の復活だが、バイデンが進めてきたLGBTQなどの性的少数者の権利拡張を撤廃して、「性」はジェンダーではなくセックスで、生物として2つしかないことを明言したのである。
・このような世界的な流れに逆らう政策は他にもあって、地球の温暖化を防ぐためにできた「COP」(国連気候変動枠組条約)に対して、バイデンが再加盟したのにまた脱退を表明しているし、コロナ対応を批判して「WHO」(世界保健機関)からも脱退しようとしている。石油はもっともっと使えばいいし、コロナなど恐れずに活発に活動したらいい。そうやってアメリカを豊かにするのだ、というのが彼の基本的な政策なのである。
・とは言え、他方でトランプはノーベル平和賞を欲しがっていて、パレスチナやウクライナなどの紛争の解決に力を入れるだろうと予測する意見もある。実際、イスラエルは一時的な停戦に合意をしたし、プーチンとゼレンスキーの間に入って戦争を終わらせるよう働きかける姿勢も見せている。中国に対しては相変わらず強圧的だが、同時に交渉を進める余地も残しているようだし、北朝鮮に対しても同様だ。そうなると日本にはどういう姿勢を見せるのだろうか。安部とは兵器の爆買いもあって仲が良かったが、石破はどうするのだろうか。トランプを怒らせず、しかし日本の立場もしっかり主張する。そんなことができなければ、日本はまずますダメになるばかりだろう。
2024年11月4日月曜日
ドジャースがワールドシリーズ制覇!
|
・ドジャースが優勝した。大谷選手にとって7年目にしてやっと手にするチャンピオンリングである。MVPを2度も取ったのに勝ち越しすらできなかったエンゼルスから移籍して1年目の快挙だった。プレイオフに出るまで最多の試合を経験した選手だったというから、彼の喜びは大変なものだろうと思う。しかし、彼についてはまた別に書くことにして、今回は彼やドジャースに対するメディアの対応について考えてみたいと思う。 ・アメリカでは野球はすでに一番のスポーツではなく、アメリカン・フットボールやバスケットの後塵を拝していると言われている。オールスター・ゲームやワールドシリーズでもテレビの視聴率は低く、それも年々下がっていると言われてきた。それが今年はドジャースとヤンキースのワールド・シリーズになって、視聴率も大幅に回復したようだ。大谷とジャッジというMVP有力選手が出ることもあって、事前の盛り上がりは例年とは違うものになった。 ・それは日本でも同様だった。日本シリーズがワールドシリーズと同じ日程で行われたのだが、NHKの7時のニュースではワールドシリーズの結果を取り上げて、同時刻に行われていた日本シリーズには全く触れなかった。MLBの中継は主にNHKのBSで行われたが、ワールドシリーズについてはフジテレビが地上波で中継した。ライブは午前中だったから、フジテレビは夜のダイジェストで再放送をしたようだ。ところがそれが日本シリーズと重なって、NPB(日本野球機構)はフジテレビの取材パスを没収したようである。 ・ただでさえ陰に隠れてしまっているのに、さらに邪魔をされた。NPBはそんな仕打ちに腹を立てたのだと思う。何しろフジテレビは日本シリーズの別の試合を中継しているのである。フジテレビと言えば、大谷選手の新居を探して、場所が特定できるような放送をして、ドジャースから取材拒否を宣告もされている。そこには、どんな影響が出ようと視聴率さえ取れればいいんだといった態度があからさまなのである。当然だが、大谷選手はフジテレビのインタビューを拒否したようだ。 ・とは言え、大谷選手の人気がテレビの視聴率やCMに大きな影響を与えていることも事実である。何しろ彼は10年で7億ドルの契約を結んだが、その大半は後払いで、山本選手などに払うお金を融通したのである。それは彼が日本の企業などと契約した額が、彼が手にする年俸を超える程だったからだと言われている。そしてスポンサー契約はドジャース自体にももたらされて、広告や入場者数やグッズの売り上げなども大幅に増加したようだ。 ・恩恵は、ドジャースが遠征したチームにももたらされている。普段は閑古鳥の弱小球団でも、大谷目当てに満員になった試合がいくつもあったからである。普通は他球団のグッズなど売らないのに大谷選手だけは例外にする。そんなこともあったようだ。チームは勝って欲しいけど、大谷選手のホームランは見たい。そんなアメリカでも一番人気の大谷選手が活躍したドジャースがワールドシリーズに出て優勝したのだから、その効果は来シーズンにももたらされるのだろうと思う。 ・ドジャースの試合を見て大谷選手の活躍を堪能したが、他方でお金にまつわる話題がつきなかったことも印象に残った。ワールドシリーズのチケット高騰や50x50を達成したボールのバカ高値などあげたら切りがないほどだった。ちなみに、ワールドシリーズの視聴者数は日本では1試合平均1210万人で過去最多だったが、同様に、台湾、カナダ、メキシコ、ドミニカでも最多だったようだ。 |
2024年10月21日月曜日
CopyTrackにご用心!
|
・このホームページは毎週一回更新している。いろいろな話題を探して書いているのだが、時にはその内容にあった画像が欲しくなる。著作権にふれないよう気をつけてネットから探していたのだが、突然、無断使用だから使用料を払えといったメールが飛び込んできた。「CopyTrack」という名称で、2枚の画像について、700ユーロ(11万円程)を払えという内容だった。悪いことをしたのだから払って当然という、極めて高飛車の文面で、ちょっと驚いてドキドキしながらネットで調べてみた。 ・そうすると同様のケースがたくさんあって、払った人、払わなかった人など様々だった。ネットに詳しい何人かの知人にもメールを出して、どう対処したらいいか相談したところ、よく調べてもらって、無視したらよろしいという返事だった。「CopyTrack」のサイトには、対象は営利の商用サイトであって、個人のサイトには要求しないとあった。だったら僕のホームページは対象外だから、要求には応えられないと返信した。 ・ところが、最初は日本語だったのに、今度は英語で、あなたの主張には応じられないとあって、同様の金額の請求が繰り返された。非営利の個人サイトであることを認めないのは大学のサーバーから発信しているせいかも知れないと思い、すでに退職して大学には所属していないこと、名誉教授の権利として、サーバーを使わせてもらっていることを書いて返信したのだが、やって来たのは問答無用の返答で700ユーロの要求を繰り返すだけだった。 ・文面には、払わなければ法的手段に訴えるとも書いてあったが、第二東京弁護士会 のサイトには「写真等の無断転載に関して金銭請求を代行する業者に注意を」というページがあった。それによると、無断転載に関する金銭請求には弁護士や認定司法書士の資格が必要で、それがなければ「非弁行為」として刑事罰の対象になると書いてあった。また「CopyTrack」のような非弁業者が弁護士に依頼して裁判に訴えることも違法だとあって、法的な手段を使うことはできないことがわかった。 ・「CopyTrack」にはプロの写真家やイラストレーターでなくても、誰でも登録できるようだ。たとえば僕のホームページにはすでに4000枚を超える画像が載っている。そのほとんどは僕が撮ったものだから、「CopyTrack」に登録すれば、無断で利用した人に使用料の請求がいくことになるだろう。そうすれば僕にもお金が入ってくることになるのだが、僕はプロではないから、そんな報酬が欲しいとは思わない。個人的に利用するのなら、どうぞご自由にというのが、僕の基本的な方針だからである。営利目的で使用したり、変な使われ方をしたことが分かれば、直接苦情を言ったり、損害賠償で訴えるといったことがあるかも知れないが、今のところそんなケースも見つけていない。いずれにしても、十分に気をつけること。今回の騒動で身にしみた戒めだった。 |
2024年8月5日月曜日
またTVはオリンピックばかりだ
・オリンピックが始まって、テレビはどこも五輪一色になった。ただでさえ見るものがないと思っていたのに、TVをもうつける気もしない。それでもニュースなどを見れば、いやでもオリンピックを見させられることになる。そんな消極的な姿勢で見ていて気づいたことがいくつかあった。一つは前回の東京から登場したスケボーである。日本人選手が活躍してメダルをいくつも取ったためか、よく報道された。
・まず気になったのは、きらきらネームの選手が多いことだった。吉沢恋(ここ)、中山楓奈(かな)、赤間凛音(りず)、開心那(ひらき・ここな)、小野寺吟雲(ぎんう)、白井空良(そら)、永原悠路(ゆうろ)などで、何と読むのかわからない名前ばかりだった。そう言えば、東京五輪でも歩夢とか勇貴斗、碧優、碧莉、椛などの名前があった。名前は親がつけるから、きらきらネーム好きはスケボー好きの人に共通した特徴なのかと妙な感心をした。
・次に首をかしげたのは、その競技そのものだった。スケボーに乗って階段の手すりに飛び移り、数メートル滑って着地するというだけのもので、これが一つの種目として成立していることが不思議だった。おそらく難しいのだろうし、その中にいくつも技が使われているのだろうが、わずか数秒の試技は、町中で見られる若者の単純な遊びにしか見えなかった。そもそもこんな種目をオリンピックでやる意味がどこにあるのか。この大会から始まったブレークダンスをふくめて、若者を惹きつけるためにIOCが見つけた苦肉の策だと言いたくなった。
・他方で野球は参加国が少ないという理由で不採用になった。次回のロサンゼルスでは復活してMLBの選手も参加できるのではと言われている。パリでの不採用はおそらく、球場をいくつも作らなければならないことが最大の理由だったのだと思う。昨年のWBCにヨーロッパの国も参加していたが、フランスという名は見かけなかった。それに比べればスケートボードやブレークダンスの会場は、ほとんどお金をかけずに作ることができる。低予算でそれなりに人気を呼べる種目で、これまでオリンピックに興味を持たなかった人を引きつけることができる。IOCのそんな目論見が露骨に感じられるのである。
・低予算といえば開会式も型破りだった。国立競技場を新たに作ったのにコロナで無観客になった東京と違って、パリではセーヌ川の両岸に特設の席を作り、各国の選手が遊覧船に乗って手を振るというものだった。歌や寸劇、あるいはファッションショーなどが、橋の上や岸辺に作られた舞台で演じられた。詳しく見たわけではないが、フランスの歴史、とりわけ革命などがテーマになって、陳腐だった東京とは対照的だったという意見も耳にした。各競技に使われる会場もほとんどが既存のもので、その意味でも、予算規模は東京とは比べ物にならないほど小さなものであるようだ。
・東京オリンピックは当初の予算の何倍も浪費した大会で、汚職が事件になり、疑惑が渦巻いたひどいものだった。今回のパリ五輪を契機に、その違いを取り上げて欲しいものだが、そんな気骨のあるメディアは日本からは消えてしまっている。そもそも東京五輪にどれほどのお金がかかり、その詳細がどうだったかは、未だに隠されたままなのである。しかも同じ失敗をまた大阪万博でやろうとしている。メダルを取って大はしゃぎのテレビをうんざりしながら見ていて思うのは、選手たちの頑張りとは対照的な、日本という国のダメさ加減ばかりである。
2024年7月29日月曜日
保険料金の高さにびっくり!
・75歳になって、今年から後期高齢者の保険料が追加されたが、その額が17万円ほどになっていることに驚いた。もちろん、これ以外に国民健康保険も5万円ほどとられている。その他に介護保険料が夫婦二人で15万円ほどだから、合わせて一年に37万円もとられたのである。しかも額が大きく、これを国民年金で収めることができないから、直接振り込んでくれというのだった。
・僕は時折歯医者に行く以外には、もう20年以上病院に行ったことがない。その間ずっと社会保険料を払い続けてきたから、総額ではもう何百万円にもなるはずだが、その恩恵はほとんど受けていない。ただしパートナーが10年ほど前に脳梗塞を患って、その後も薬を飲んでいるから、それなりの恩恵は受けてきたことになる。しかし、パートナーが75歳になれば、保険料は一人づつになって、その額は国保の二人で5万円から30万円超になるから、年金暮らしの身には、とんでもない高負担が請求されるのである。
・ちょっとひどいんじゃないかと思って調べると、それでも高齢者自身の負担は1割で、あとは国や自治体、そして若い人たちが収める保険料で負担されるとあった。団塊の世代が後期高齢者になって、その医療費や介護費が増加している。そのために当事者にもそれなりの負担をお願いするというのが、国や自治体の説明だった。確かに増大する一方の医療費や介護費を捻出するためには、ある程度の本人負担が求められるのも仕方がないだろう。しかし、75歳になったからはい増額というのは、お役所仕事といわざるを得ないだろう。国民年金しか収入のない人は、一体どうやって払うというのだろうか。
・後期高齢者保険料の通知には、ほかにも気に入らないことがあった。マイナカードを取得して、保険証に使えるよう速やかに登録せよというお達しである。僕はマイナカードは持っていないし、持つつもりもないから、今までの保険証を使い続けるつもりである。そのためには資格確認書を取得しなければならない。そういう国の意に従わない者には自分で手続きをしてもらう。河野担当大臣はそんな脅しめいた発言をしていたが、ネットで確認すると、何もしなくても送られてくるようである。
・マイナカードはあらゆる手続きのデジタル化をめざして作られたことになっている。しかし、デジタル化というのはスマホなどで用が足せるようになるということであるから、マイナカードは何とも中途半端な制度だと言わざるを得ない。住基ネットなどで失敗しているのにまた同じことをやっている。しかも今度は普及させるために金で釣り、脅しをかけてのことだが、その普及率はなかなか上がらないのである。
・お札が新しくなったが、僕はまだ手にしていない。使うお金のほとんどはクレジットカードだし、必要なものの多くはネットで買っているからだ。しかしスーパーなどで見ると、現金で買っている人が多いから、お札の利用状況はまだまだ高いのだろう。未だにハンコを要求されることが多いことも含めて、日本人の多くはデジタルではなくアナログに馴れたままなのである。この意識や行動をどうやって変えて行くか、それは何年も前から国や自治体が本気になってやるべきことだったはずである。
・話がずれてしまったが、医療費の高騰を避けるために一つ考えていることを最後にあげておこうと思う。それは終末医療の問題で、延命治療には保険を適用しないという制度を実現させる必要があるということだ。『欧米に寝たきり老人はいない』でも書いたが、僕の母親は今、意識がないままに延命治療を受けている。咳払いをして痰を飲み込んだり、手を握ると握り返してきて、しっかり生きていると実感できるが、これをいつまでも続けてはいけないとも思っている。僕自身はもちろん、多くの日本人にとって延命治療をやめる決断はしにくいことだが、その膨大な医療費を考えたら、どこかで、国民が納得する方策を国が提案しなければならないが、そんな勇気ある決断は誰もやらないだろうとも思っている。
2024年7月1日月曜日
国会が終わり、都知事選が始まったけれど………
|
・国会が終わり、都知事選が始まった。政治資金規正法改正だけの国会だったが、それも結局ザル法のままだった。円安が止まらず、貿易収支も赤字で、実質賃金は減り続けているというのに、ほとんど対応策がとれないままに、国会が終わったのである。岸田政権の支持率はずっと下がり続けていて、調査によっては17%という数字になっている。本来なら倒れていて当然の数字だが、当の首相は全く気にしていないようだ。 ・一番の要因はメディアの批判の甘さだろう。政権が支持されていないこと、政治資金規正法が手ぬるいと非難されていることを、世論調査を根拠に指摘しても、新聞が自ら、厳しく批判することはどこからも起こらなかった。自民党は最近の選挙でほぼ全敗している。世論調査でもその点ははっきりしていて、政権交代を希望、あるいは予測する人は半数を超えている。ただし、立憲民主党が政権奪取に向けて本腰を入れているわけではないから、衆議院選挙をしても、自民党が下野するところまでは行かないだろう。 ・そんな曖昧な状況はメディアにとっては好都合だということかも知れない。政府に頭を押さえられたNHKは言うまでもなく、民放はスポンサーと電通頼りだし、大手の新聞社だって、基本的には政権交代を望んではいないのである。日本は一体どこまで落ちるのか。改善策を見つけられない八方ふさがりの状態なのに、政治家も官僚も、そしてメディアも、自己保全のことしか考えていない。そんな態度や姿勢ばかりが目立つのである。 ・都知事選は小池百合子が3選をめざしている.蓮舫が立候補して二人の争いになっているが、調査では小池が圧倒しているようだ。大きな失政はないとは言え、先の選挙で公約した7つのゼロの多くは実現していない。神宮外苑の開発問題もあるし、何より学歴詐称の一件もある。しかしここでもまた、メディアはこのような点について強い批判を浴びせてはいない。フリーのジャーナリストを締め出した記者会見が当たり前になっていて、そこでは小池がいやがる質問は、ほとんど出ないようだ。非難を浴びせられる都内の街頭演説は避けて、八丈島や奥多摩に出かけている。集まる人は少ないが、テレビのニュースではトップに報道するから、それでも効果は絶大だろう。 ・都知事選には56人が立候補したようだ。中にはヌードのポスターを貼ったりする人もいて、一体何のためにと疑ってしまう。売名行為なのか、YouTubeやInstagramでのアクセス数を狙っているのか。そう言えば、衆議院議員の補選では他候補の邪魔をして逮捕された候補者もいて、YouTubeではかなりのアクセス数を獲得したようだ。こんな話ばかり耳にすると、もう世も末だと思わざるを得ない。どうせ誰が何をやったって、日本はもう経済的に復活などしない。だったら今だけ金だけ自分だけ。面白おかしく楽しくやろう。他人を傷つけたって構わない。そんな空気は何より最近のテレビにも溢れている。 |
2024年5月27日月曜日
田村紀雄監修『郡上村に電話がつながって50年』 クロスカルチャー出版
・監修者の田村紀雄さんはもう米寿になる。毎年のように本を出しているが、今年も送られてきた。いやいやすごいと感心するばかりだが、この本は50年前からほぼ10年おきに調査を重ねてきた、その集大成である。彼と同じ大学に勤務している時に、同僚や院生、それに学部のゼミ生を引き連れて、調査に出かけているのは知っていた.その成果は大学の紀要にも載っていたのだが、半世紀も経った今頃になってまとめられたのである。
・調査をした場所は岐阜県で郡上村となっているが、このような村は今もかつても存在していない。場所や人を特定されないための仮称で、現在は郡上八幡市に所属する一山村である。田村さんはなぜ、この地を調査場所として選んだのか。それは一つの小さな集落が、電話というメディアが各戸に引かれることで、それ以後の生活や人間関係、そしてその地域そのものがどのように変化をしていくか。それを見届けたいと思ったからだった。始めたのは1973年で、まさにこの村にダイヤル通話式の電話が引かれるようになった年である。そのタイミングのよさは、もちろん偶然ではなく、情報が田村さんの元に届いていて、長期の調査をしたら面白いことがわかるのではという期待があったからだった。
・「郡上村」は長良川の支流沿いにある谷間の山村で、この時点の世帯数は1200戸ほどだった。村には手広く林業を営む家があり、そこがいわば名主のような役割をしてきた歴史がある。この家にはすでに昭和4年に電話が引かれていたが、それは個人で費用を負担したものだった。戦後になって1959年に公衆電話が設置され、村内だけで通話ができる有線放送も63年からはじまったが、村外との個別の通話が可能になったのは1973年からだった。
・被調査に選んだのは数十戸で、調査の対象は主として主婦だった。この村ではすでに村内だけで通話ができる電話があって、村内でのコミュニケーションには役立っていたが、村外とのやり取りが当たり前になるのは、10年後、そして20年後に行った調査でも明らかである。ここにはもちろん、仕事や学業で家族が外に出る。あるいは外から婚姻などでやって来たり、外に嫁いでいくといったことが一般的になったという理由もあった。日本は1960年代の高度経済成長期から大きな変貌を遂げ、人々が都市に集まる傾向が強まったが、この村でもそれは例外ではなかったのである。
・ただし、人々の都市集中や人口の減少で、眼界集落が話題になり、最近では市町村の消滅が問題にされているが、「郡上村」の人口は現在でも、大きく減少しているわけではない。そこには電話や今世紀になって一般的になったスマホやネットだけでなく、クルマの保有や道路の整備などで、近隣の都市に気軽に出かけることが出来るようになったという理由がある。あるいは工場が誘致されて、働き口が確保されたということもあった。
・しかし、この半世紀に及ぶ調査で強調されているのは、結婚によって外からやってきた女性たちの存在だった。その人たちが、村の閉鎖的な空気を開放的なものに変えていった。面接調査を主婦に焦点を当てて行ったことが見事に当たったのだった。
2024年5月20日月曜日
SNSはもうやめた
|
・SNSについては今まででも熱心ということはなかった。やっていたのはTwitterとFacebookだけで、lineもInstagramにも無関心だった。Twitterは、政治や社会に対して同意できたり、参考になったりする発言をリツイートするぐらいで、自分からツイートすることはほとんどなかった。だから、フォローする人も少なかったし、フォローしてくれる人もほとんどなかった。Facebookはすでに知っている人だけに限定して、知らない人と友達になることはなかったし、「いいね」で反応することもほとんどしなかった。 ・そんな程度のつきあいだったから、TwitterがXに変わったことをきっかけに、アクセすることも少なくなった。FacebookはCMが増えて、商業主義的な色合いが強くなり、やたら友達候補を並べるのにうんざりして、ちょっと前から全く見なくなった。もうどちらもやめてしまってもいいのだが、やめる手続きをすることも面倒だから、そのままにしている。 ・そんな具合だから、自分では見たことがないのだが、有名人を騙って投資を呼びかける投資詐欺が話題になっている。警察庁の調べによれば24年1月〜3月だけで1700件が確認され、被害額は200億円を超えているそうである。よくあるのは著名人の画像を貼りつけ、本人になりすまして投資の勧誘をするというもので、本人だと思った人が、言われるままに投資して、それをだまし取られるというものである。 ・自分の名前をかたった詐欺で被害を受ける人がいることに怒った著名人が、lineやFacebookに対応を求めたようだが、その反応は極めて消極的だったようだ。そもそもこの手の詐欺は、広告として掲載されているからサイトの大きな収入源になっているのである。これでは詐欺の片棒を担いでいるといわれても仕方がないのだが、今のところ取り締まる法律が整備されていないから、野放し状態のようである。 ・詐欺といえば電話を使った〔オレオレ詐欺」が有名で、その被害も未だになくなっていない。実際僕の家の電話にも、それらしいものがよくかかってくる。迷惑電話防止モードにして「お名前を仰ってください」と告げるようにしているから、何も言わずに切ってしまうことがほとんどだが、うっかりでたら、その話に乗ってしまうことが多いのだろうと思う。 ・SNSは地縁や血縁の関係が弱くなった現在の社会のなかで、それに変わる人間関係の持ち方として発展してきた。それを使っていい関係を作れる場合が多いのはもちろん、否定しない。しかし-このままでは、電話に変わる詐欺の手段として使われるようになってしまうだろう。くわばらくわばらである。一番の対応策は、SNSをやめることで、そのことで不便さを感じることはなにもないだろうと思う。 |
2024年4月29日月曜日
地震対応に見るこの国のお粗末さ
・しかし、もっと驚いたのは花蓮で避難所を設置する様子で、それほど時間が経っていないのに、体育館にずらっと個室が並んでいたのである。まだ被災者がほとんどいないのに食べ物や衣料など、必要なものも整えられているという報道だった。日本では正月に能登の地震があって、相変わらずの体育館に雑魚寝の様子が伝えられていたから、その違いに驚かされた。
・花蓮は最近でも2018年と22年に大きな地震に見舞われていて、その度に大きな被害を受けている。だから地震に対する備えが出来ていたのだろう。報道では、台湾の災害対応は1999年の地震以後に日本から学んだということだった。花蓮では2018年の地震でうまく対応できなかったことを反省して、必要なものの備蓄を整え、人々の訓練も行われてきたと報じられた。傾いたビルの撤去がすぐに始まったことにも感心させられた。花蓮では23日にも大きな余震があってビルが傾くなどの被害があった。おそらくまた迅速な対応をしているのだと思う。 ・ところが日本では能登地震から4ヶ月が過ぎようとしているのに、未だに避難所生活をしている人がいる。家が住める状態だとしても、上下水道が普及していないところが多いようだ。仮設住宅の建設もほとんど進んでいないのである。倒壊した建物や、破損したクルマがそのままに取り残された光景を見ると、4ヶ月も経っているのに、いったい何をしているんだろうと怒りたくなる。 ・もっともテレビは、そんな普及の遅さを批判的に伝えたりはしない。水道が使えないのにレストランやカフェを営業しているなどといった事例を美談のようにして紹介するものが多いのである。政府や県の対応のまずさ、というよりはやる気のなさが目立つのに、強く批判するメディアがほとんどないという現状には呆れるばかりである。ネットでフリーのジャーナリストの現地報告を何度か聞いたが、能登の人たちがまさに棄民状態に置かれたままであることを一様に話していた。被災した人たちの政府や自治体、そしてメディアに対する不信感はかなりのものようだ。政治もダメだがジャーナリズムもダメ。この国のお粗末さは、いったいどこまでひどくなるのだろうかと空恐ろしくなる。 |
-
・ インターネットが始まった時に、欲しいと思ったのが翻訳ソフトだった。海外のサイトにアクセスして、面白そうな記事に接する楽しさを味わうのに、辞書片手に訳したのではまだるっこしいと感じたからだった。そこで、学科の予算で高額の翻訳ソフトを購入したのだが、ほとんど使い物にならずにが...
-
12月 26日: Sinéad O'Connor "How about I be Me (And You be You)" 19日: 矢崎泰久・和田誠『夢の砦』 12日: いつもながらの冬の始まり 5日: 円安とインバウンド ...
-
12月 22日 国会議員の定数より歳費の削減を! 15日 鉄道旅に見る中国の変容 8日 紅葉が終わった 1日 工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社 11月 24日 『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』 17日 仕事を辞めて8年も経った? 10日 ドジャース...