 |
 ・今年も二人だけの静かな正月を迎えた。お節はいつもの通りほぼ手作りで、僕は伊達巻きを作った。三が日はお雑煮だったが、おもちは日常的に食べている。僕の得意料理は餅ピザで、これはネットでもあまり見かけないオリジナルだ。この冬は11月から寒くて、薪の消費量は例年になく多い。蓄えは十分にあるのだが、どんどん減っていくと不安な気持ちにもなる。  ・そんなふうに思っていたら、暮に近所でケヤキの大木の伐採があって、すぐに欲しいとお願いに行った。そうするといいですよという返事で、何と根元から細枝まで置いていった。まずは玉切りしやすい太さのものを切って、斧で割って右のように2mほどに積み上げた。細枝も短く切って中に詰め込んである。ここまで一ヶ月ほどかかったが、節も多いし、木も固いから簡単ではなかった。チェーンソーの調子が悪くて点火プラグの交換をした。少しましになったが力不足はどうしようもない感じだ。何しろ根元は1mほどの太さがあって、それを玉切りするのは簡単ではないのである。  ・僕は気にならなかったが、パートナーが臭い臭いと言う。ネットで調べるとケヤキにはアンモニア臭があるという。乾燥させれば臭いは消えるとあったから、薪としては問題ないだろうと思う。ケヤキは家具材としても使われているが、その特徴は何より強靱さや粘りにあるようだ。それはチェーンソーの切り具合や、斧を打ち込んだ時の手強さでもよくわかった。もらった木も製材したら一枚板が何枚も取れるのだが、人気がなくて輸入材に比べて安価なようだ。
・僕は気にならなかったが、パートナーが臭い臭いと言う。ネットで調べるとケヤキにはアンモニア臭があるという。乾燥させれば臭いは消えるとあったから、薪としては問題ないだろうと思う。ケヤキは家具材としても使われているが、その特徴は何より強靱さや粘りにあるようだ。それはチェーンソーの切り具合や、斧を打ち込んだ時の手強さでもよくわかった。もらった木も製材したら一枚板が何枚も取れるのだが、人気がなくて輸入材に比べて安価なようだ。 ・そんなわけで厳寒の中、堅物の大物と格闘中である。とりあえずは玉切りにはしたが、すべてを薪にしてアルプス積みにするには、まだ一ヶ月はかかるだろう。それでも、これでこの冬の薪の消費量を補えるかというと、ちょっと心細い。何しろ三ヶ月ほどでアルプス積みの三個分をほぼ燃やしてしまったのである。早く春にならないかと願うばかりである。 |


 ・最近はめったに歩かなくなったが、せめて紅葉台ぐらいはと行ってきた。ちょうど紅葉も見頃で、富士山も雲間から時折顔を出した。湖畔は観光客でいっぱいだが、ここまで来る人は少ない。急に寒くなったせいか、今年の紅葉はきれいだ。富士山の初雪も去年よりはずっと早く、10月末には薄化粧になって、11月にはかなり白くなった。
・最近はめったに歩かなくなったが、せめて紅葉台ぐらいはと行ってきた。ちょうど紅葉も見頃で、富士山も雲間から時折顔を出した。湖畔は観光客でいっぱいだが、ここまで来る人は少ない。急に寒くなったせいか、今年の紅葉はきれいだ。富士山の初雪も去年よりはずっと早く、10月末には薄化粧になって、11月にはかなり白くなった。



 ・11月の上旬に朝起きると急に右目のまぶたが重く感じるようになった。すぐ直るかもと、しばらく放っておいたが全然良くならない。毎年の健康診断の日に行くと、血圧がとんでもない高さになっていて、これは脳にでも原因があるのではと不安になって、脳神経外科に行った。そうするとCT検査をして副鼻腔炎と診断された。2週間の吸入と薬で副鼻腔炎は直ったと言われたのだが、まぶたはまだ引っかかった感じがする。鼻水が出るしくしゃみも良くするから、まだ完治していないのかも知れない。
・11月の上旬に朝起きると急に右目のまぶたが重く感じるようになった。すぐ直るかもと、しばらく放っておいたが全然良くならない。毎年の健康診断の日に行くと、血圧がとんでもない高さになっていて、これは脳にでも原因があるのではと不安になって、脳神経外科に行った。そうするとCT検査をして副鼻腔炎と診断された。2週間の吸入と薬で副鼻腔炎は直ったと言われたのだが、まぶたはまだ引っかかった感じがする。鼻水が出るしくしゃみも良くするから、まだ完治していないのかも知れない。
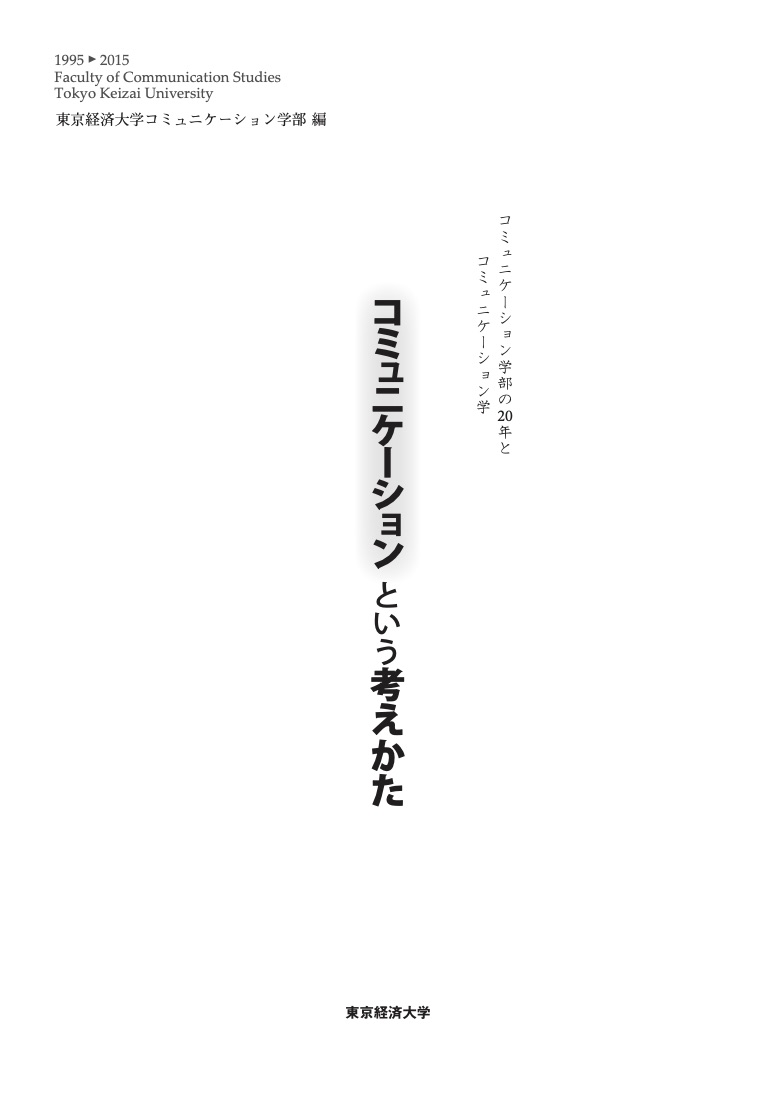 ・そこで辞めた年を確認すると2017年となっていて、改めて、もう8年も経ったんだと気づかされることになりました。そう言えば、辞めてから大学には一度も行っていないのです。もちろん、卒業式や入学式、ホームカミングデイなどの誘いの手紙はやって来ます。しかし特に行きたいとは思いませんし、行かなければならない義務もありませんから、いつも欠席と書いて返答していました。大学には18年勤めましたが、たまには行ってみたいなどとも思わなかったのです。
・そこで辞めた年を確認すると2017年となっていて、改めて、もう8年も経ったんだと気づかされることになりました。そう言えば、辞めてから大学には一度も行っていないのです。もちろん、卒業式や入学式、ホームカミングデイなどの誘いの手紙はやって来ます。しかし特に行きたいとは思いませんし、行かなければならない義務もありませんから、いつも欠席と書いて返答していました。大学には18年勤めましたが、たまには行ってみたいなどとも思わなかったのです。
 ・ところで彼岸までは猛烈に暑かったのに、10月になると秋らしいというよりは、もう冬かという日が何度かあった。それが夏のぶり返しのような日と交互にやって来るから、身体には良くないと思う。おまけに雨の日が多い。そんな冷たい雨が降る翌日に富士山が初冠雪の姿を現した。例年より3週間も遅いそうだが、去年よりは1ヶ月も早かった。
・ところで彼岸までは猛烈に暑かったのに、10月になると秋らしいというよりは、もう冬かという日が何度かあった。それが夏のぶり返しのような日と交互にやって来るから、身体には良くないと思う。おまけに雨の日が多い。そんな冷たい雨が降る翌日に富士山が初冠雪の姿を現した。例年より3週間も遅いそうだが、去年よりは1ヶ月も早かった。 ・そんなわけで、灯油を買いに出かけた。18Lを6缶で108Lだが、これでは空にしたファンヒーターと工房の床暖、それに給湯に入れたらお終いで、続けてもう一回買うことになった。寒い日にはアラジンストーブをつけ、夜はファンヒーターをセーブ運転にしている。これでまあまあ温かいが、最低気温が零度近くまで下がったら、薪ストーブも燃やそうと思っている。去年よりは一ヶ月も早いが、ちょっと前までは10月の後半には燃やしはじめていた。暑い日が長くなって、すぐに寒くなるのでは、秋がますます短くなってしまう。
・そんなわけで、灯油を買いに出かけた。18Lを6缶で108Lだが、これでは空にしたファンヒーターと工房の床暖、それに給湯に入れたらお終いで、続けてもう一回買うことになった。寒い日にはアラジンストーブをつけ、夜はファンヒーターをセーブ運転にしている。これでまあまあ温かいが、最低気温が零度近くまで下がったら、薪ストーブも燃やそうと思っている。去年よりは一ヶ月も早いが、ちょっと前までは10月の後半には燃やしはじめていた。暑い日が長くなって、すぐに寒くなるのでは、秋がますます短くなってしまう。 ・それは生き物にも言えるのだろうか。秋口になって屋根の軒に蜂が巣を作りはじめて、あっという間にご覧のような大きなものになった。ところが寒くなったら、しきりに飛び交っていた蜂が見えなくなった。春からならともかく、こんな時期に一体何のために巣作りをしたのだろうか。最近の気候変動は生き物にとっても予測しがたいものなのかもしれない。
・それは生き物にも言えるのだろうか。秋口になって屋根の軒に蜂が巣を作りはじめて、あっという間にご覧のような大きなものになった。ところが寒くなったら、しきりに飛び交っていた蜂が見えなくなった。春からならともかく、こんな時期に一体何のために巣作りをしたのだろうか。最近の気候変動は生き物にとっても予測しがたいものなのかもしれない。
 ・一昨年は上高地に行ったので、今回は乗鞍に行くことにした。道はマイカー禁止でバスで行くのだが、乗り場には上の畳平は濃霧で強風とあった。乗客は僕らともう二人だけ。行っても何も見えないとは言え、ひょっとしたら急に霧が晴れるかもと期待して、行くことにした。しかし、徐々に霧が濃くなり、畳平は雨が降って風も強く、とても歩ける状況ではなかった。仕方なく待合所にいてすぐにバスで下山した。
・一昨年は上高地に行ったので、今回は乗鞍に行くことにした。道はマイカー禁止でバスで行くのだが、乗り場には上の畳平は濃霧で強風とあった。乗客は僕らともう二人だけ。行っても何も見えないとは言え、ひょっとしたら急に霧が晴れるかもと期待して、行くことにした。しかし、徐々に霧が濃くなり、畳平は雨が降って風も強く、とても歩ける状況ではなかった。仕方なく待合所にいてすぐにバスで下山した。





 ・帰りはいつものように八ケ岳の農場に寄って野菜を買った。まさに収穫を感謝するかのように、大小のカボチャが並んでいた。それにしても上高地から松本に行く158号線はいつ走っても怖い。暗くて狭いトンネルでのバスとのすれ違いなどヒヤヒヤものだ。何しろバスやダンプはセンターラインをはみ出して来るのである。そんなわけで、久しぶりの長距離運転は心底くたびれた。
・帰りはいつものように八ケ岳の農場に寄って野菜を買った。まさに収穫を感謝するかのように、大小のカボチャが並んでいた。それにしても上高地から松本に行く158号線はいつ走っても怖い。暗くて狭いトンネルでのバスとのすれ違いなどヒヤヒヤものだ。何しろバスやダンプはセンターラインをはみ出して来るのである。そんなわけで、久しぶりの長距離運転は心底くたびれた。

 ・以前からあったミョウガは、畑にしたところを根こそぎにしたにもかかわらず、その周囲に広がったところから100個以上の収穫があって、今でも毎日いくつか見つけている。梅酢に漬けたり、薄切りして冷凍したりしたから、来年の収穫時まで楽しむことができるだろう。もちろん毎食のメニューにも入れているが、香りが強いから少し飽きてきた。
・以前からあったミョウガは、畑にしたところを根こそぎにしたにもかかわらず、その周囲に広がったところから100個以上の収穫があって、今でも毎日いくつか見つけている。梅酢に漬けたり、薄切りして冷凍したりしたから、来年の収穫時まで楽しむことができるだろう。もちろん毎食のメニューにも入れているが、香りが強いから少し飽きてきた。

 ・今年植えた中で、全然ダメだったのがネギで、これは植える時期をずらすことにした。アスパラはそのままにして来年の収穫に期待するつもりだ。これから収穫する楽しみはサツマイモで、収穫した後のジャガイモの所にはりだして、元気にしている。葉が枯れはじめたら収穫ということだから、まだもう少しかかるだろう。どんなイモが育っているか楽しみだ。
・今年植えた中で、全然ダメだったのがネギで、これは植える時期をずらすことにした。アスパラはそのままにして来年の収穫に期待するつもりだ。これから収穫する楽しみはサツマイモで、収穫した後のジャガイモの所にはりだして、元気にしている。葉が枯れはじめたら収穫ということだから、まだもう少しかかるだろう。どんなイモが育っているか楽しみだ。

 ・ 大地震が来るといった予言でアジアからの団体客が一時激減したようだ。とは言え、湖畔に出れば主に白人の観光客の多さは相変わらずだ。日盛りでもものともせず自転車に乗ったり歩いたりして湖畔で楽しんでいる。
・ 大地震が来るといった予言でアジアからの団体客が一時激減したようだ。とは言え、湖畔に出れば主に白人の観光客の多さは相変わらずだ。日盛りでもものともせず自転車に乗ったり歩いたりして湖畔で楽しんでいる。




 ・3月末に購入してしばらくは、その日の天気や湿度に合わせて加湿だったり除湿だったりしましたが、5月になると、せっせと除湿をするようになりました。梅雨の前触れで雨の日が続きましたが、湿度は60%前後で推移して、例年ならかび臭くなる時期になってもその気配がありませんでした。6月になると真夏のような温度になり、我が家でも30度を超える日が数日ありました。その時、天気予報を見て、湿度は温度の上昇とともに下がることに気づきました。そこで日中の数時間は窓を開放して風を入れることにして、夕方から朝にかけては窓を閉めて除湿器を使うことにしました。これで何とか60%台後半の湿度を保たせることができています。
・3月末に購入してしばらくは、その日の天気や湿度に合わせて加湿だったり除湿だったりしましたが、5月になると、せっせと除湿をするようになりました。梅雨の前触れで雨の日が続きましたが、湿度は60%前後で推移して、例年ならかび臭くなる時期になってもその気配がありませんでした。6月になると真夏のような温度になり、我が家でも30度を超える日が数日ありました。その時、天気予報を見て、湿度は温度の上昇とともに下がることに気づきました。そこで日中の数時間は窓を開放して風を入れることにして、夕方から朝にかけては窓を閉めて除湿器を使うことにしました。これで何とか60%台後半の湿度を保たせることができています。









