|
・2月になって、もうすぐキャンプが始まります。今年はWBCですから、もうすぐにぎやかになるでしょう。WBCを見るためにNetFlixに加入するかどうかはまだ決めていません。月額890円ですから直前になって判断しようと思っています。当然、日本は連覇を狙っていますが、アメリカもドミニカも本気で戦力を整えてきています。さてどうなるでしょうか。 ・今年のドジャースですが、当然地区優勝は堅く、リーグ優勝も本命です。うまくいけばワールド・シリーズ3連覇も可能で楽しみだと言いたいところですが、オフの戦力補強には首をかしげることが多かったです。2連覇して最強の軍団なのに、外野とリリーフが穴だと言われ、あいつをとれ、こいつがいいといった記事が連日取りざたされました。しかしさっぱり動かないので、僕は現有勢力で来シーズンも行くのだろうと思いました。期待外れだった選手が復活するかもしれませんし、マイナーにいる若手の成長も期待できるのです。 ・ドジャースには有望な若手がたくさんいます。しかし、トレードやFAで補強を繰り返しているので、なかなかメジャーに上がってこられません。そんな選手が他球団にトレードされて、それなりに活躍しているのを見ると、出さずにチームの戦力にした方がいいのでは、と何度も思いました。何しろドジャースの一番の欠点はチームの高齢化で、20代のレギュラー選手は外野のパヘスしかいないのです。すぐに結果が出なくても我慢して使い続けることをしなければ若手は成長できません。パヘスは例外的に我慢して使って実力を出しはじめた選手なのです。 ・ドジャースはすでに選手に支払う年俸がメジャートップで莫大な贅沢税を払っています。今シーズンの終了後には選手会とオーナーが結んでいる労使協定が失効して改訂をしなければなりません。年俸のチーム上限を定めるサラリーキャップ制の導入をオーナー達が主張すれば、選手会と対立してストとロックアウトでシーズンが始まらないのではと心配されています。25年度の贅沢税を払ったのは9チームで全体の3割でした。財政豊かな球団はそんなことお構いなしにこのオフも戦力補強に多額のお金を費やしました。 ・ドジャースは結局、クローザーのエドウィン・ディアスと外野手のカイル・タッカーを取りました。ディアスは3年で6900万ドル、タッカーは4年で2億400万ドルの超高額契約でした。これで弱点と言われたリリーフと外野を補強したわけで、まさに悪の帝国といわれても仕方がないのだと思います。大谷との契約以降、ドジャースの収入は爆上がりしていますから、財政的には何の問題もないのでしょう。しかしリーグでの不均衡なチーム力は大きくなるばかりですから、他球団にとっては戦う前からギブアップということにもなりかねません。 ・選手は生身の身体ですから故障やスランプで期待外れといったこともおこるでしょう。実際去年も一昨年も、ドジャースはそんな選手たちに悩まされました。だからこその補強なのですが、毎年あまりに露骨にやっているので、もうドジャースを応援するのはやめようかと思うようになりました。大谷や山本や佐々木の応援はするけれども、ドジャースの応援はしたくない。そんなことができるのかどうか、何とも悩ましいかぎりです。 |
2026年2月9日月曜日
ドジャースの戦力補強に違和感
2025年12月1日月曜日
工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社
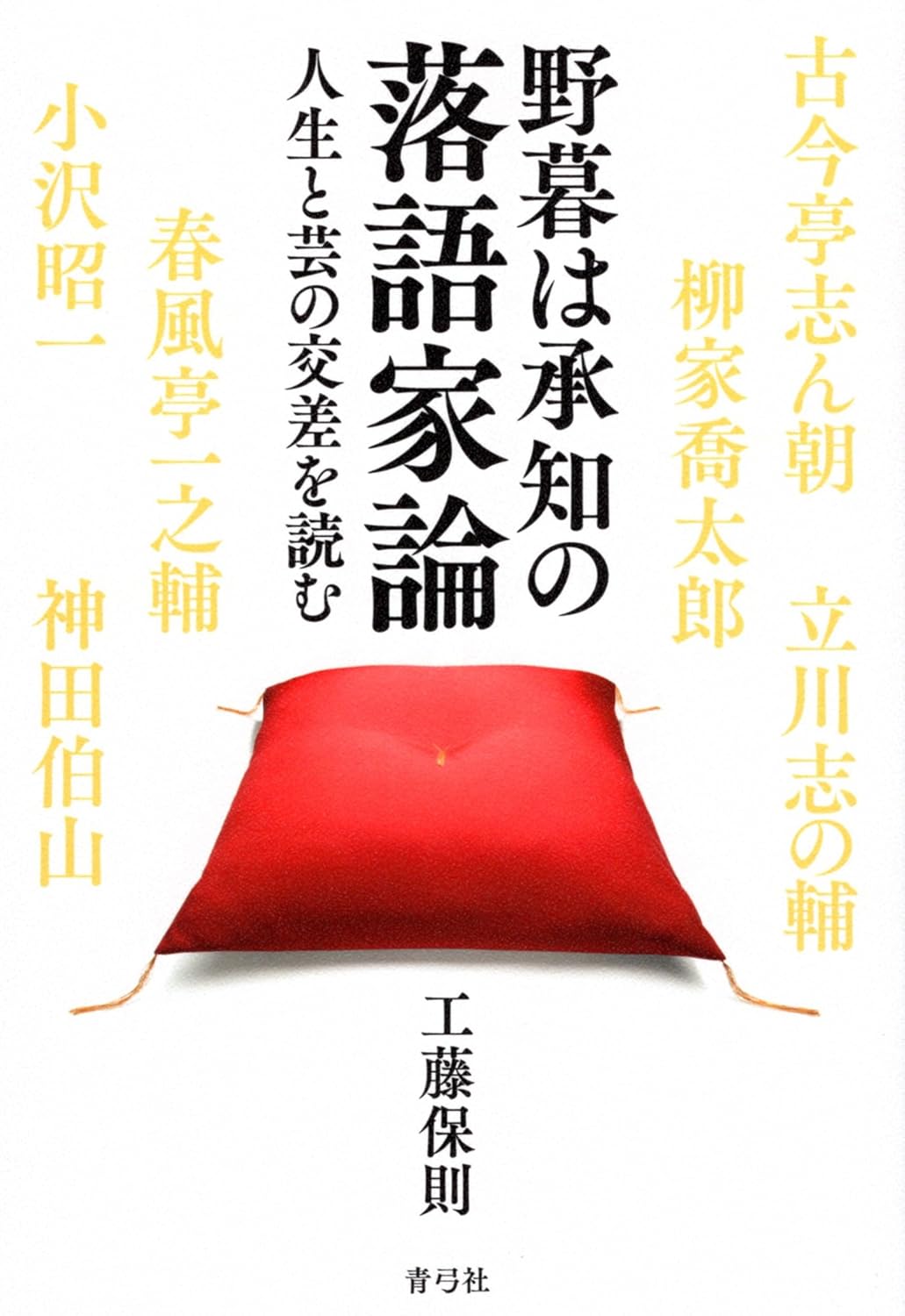 ・工藤さんから本が届いた。二冊目で、前のは『46歳で父になった社会学者』だったが、今度は『野暮は承知の落語家論』である。まるで違うテーマだが、そう言えばずいぶん前に『三田落語会』というCDのボックスを彼からいただいていた。落語好きは知っていたが、まさか本まで出すとは思わなかった。いただいたからには紹介しなければいけないが、僕は落語にはあまり興味がない。京都にいる頃はテレビで米朝や枝雀、文珍や鶴瓶などを聞くことはあったが、最近は全く聞かなかった。
・工藤さんから本が届いた。二冊目で、前のは『46歳で父になった社会学者』だったが、今度は『野暮は承知の落語家論』である。まるで違うテーマだが、そう言えばずいぶん前に『三田落語会』というCDのボックスを彼からいただいていた。落語好きは知っていたが、まさか本まで出すとは思わなかった。いただいたからには紹介しなければいけないが、僕は落語にはあまり興味がない。京都にいる頃はテレビで米朝や枝雀、文珍や鶴瓶などを聞くことはあったが、最近は全く聞かなかった。・この本で取り上げられている落語家は古今亭志ん朝、立川志の輔、柳家喬太郎、春風亭一之輔、小沢昭一、そして神田伯山である。志ん朝は昔に聞いた記憶はあるが、他の人はない。それに小沢昭一は役者だし、伯山は講談師だ。さて困ったと思ったが、とりあえずはYouTubeで探して聞いてみることにした。志ん朝は若手の有望格として若旦那を話すことに長けていたが、落語協会の分裂騒動などがあって、名実ともに旦那に磨き上げられていく。そんな説明には何となく納得できたが、後の喬太郎や一之輔は全くピンと来ない。柳家喬太郎には「間の可能性」、春風亭一之輔には「生活者の了見」というタイトルがついているが、話を一つ二つ聞いたぐらいでわかるはずもない。そんな諦めが先に立った。 ・しかし、テレビの司会で知っていた立川志の輔と師匠の談志の関係は面白かったし、小さい頃から落語に馴染み、大学から演劇に進んだ小沢昭一の話も面白かった。志の輔の章は「座布団の上の演劇」となっていて、「志の輔は登場人物に感情を込め、一人ひとりの人物になりきろうとする」とあった。確かにいくつか聞いた新作落語には、そんな特徴が見て取れた。それが談志譲りであることは古典である「芝浜」を談志と志ん朝で聞き比べてよくわかった。志ん朝は滑らかな口調で話すのだが、談志は確かに登場人物を演じていたのである。 ・小沢昭一は特異な性格俳優だったが、晩年には日本の放浪芸を訪ねて、レコードや本を出している。落語で育ち、新劇に転じて舞台や映画で活躍するが、そこに安住できずにまた落語の世界に戻っていく。小沢昭一は好きな俳優で、その放浪芸への傾注や自らを河原乞食と名乗った時期には、熱心に見聞きし書いたものを読んだこともあった。しかしその彼が寄席に戻って、舞台で話をし、ハーモニカを吹いたことは知らなかった。 ・最後の章は講談師の神田伯山で、これについてもさっぱりだったが、落語が直接聞き手に話しかけるのに講談は本を読んで聞かせる芸だとあって、あそうか、と思うところがあった。つまりコミュニケーションには三つのパターンがあって、まずは落語のように直接語る「参加」と、語りを傍観者として「立ち聞き」する形の違いがあるということだ。講談で語られる世界は本の中にあるのだから、話す者も聞く者もその世界には入れないのである。新劇は舞台と客席を断絶させて、舞台の俳優たちはあたかも客などいないかのようにして演じていく。だから観客はいわば「のぞき見」するように物語を体験するのである。映画は最初から、その形を前提にしてつくられている。 ・「参加」と「傍観」と「覗き」はもちろん、僕がコミュニケーション論を考える際に採用した解釈であって、この本に登場するものではない。しかし、よくわからないなりに読んで、僕なりに納得した点があったことはおもしろかった。とは言え、これで落語に目覚めたかと言うと、そうでもないなと思う自分がいることも確かである。 |
2025年11月17日月曜日
仕事を辞めて8年も経った?
・勤めていた大学から久しぶりに手紙が来ました。開けると学部の創立30周年記念のシンポジウムの案内で、その出欠を問うものでした。行こうかどうしようか迷いましたが、その前に30年という数字に驚きました。確か20周年の時には『コミュニケーションという考え方』という本を作って、僕が編集を任されたのでした。僕にとってはそれがまだついこの間のことのように思われたのです。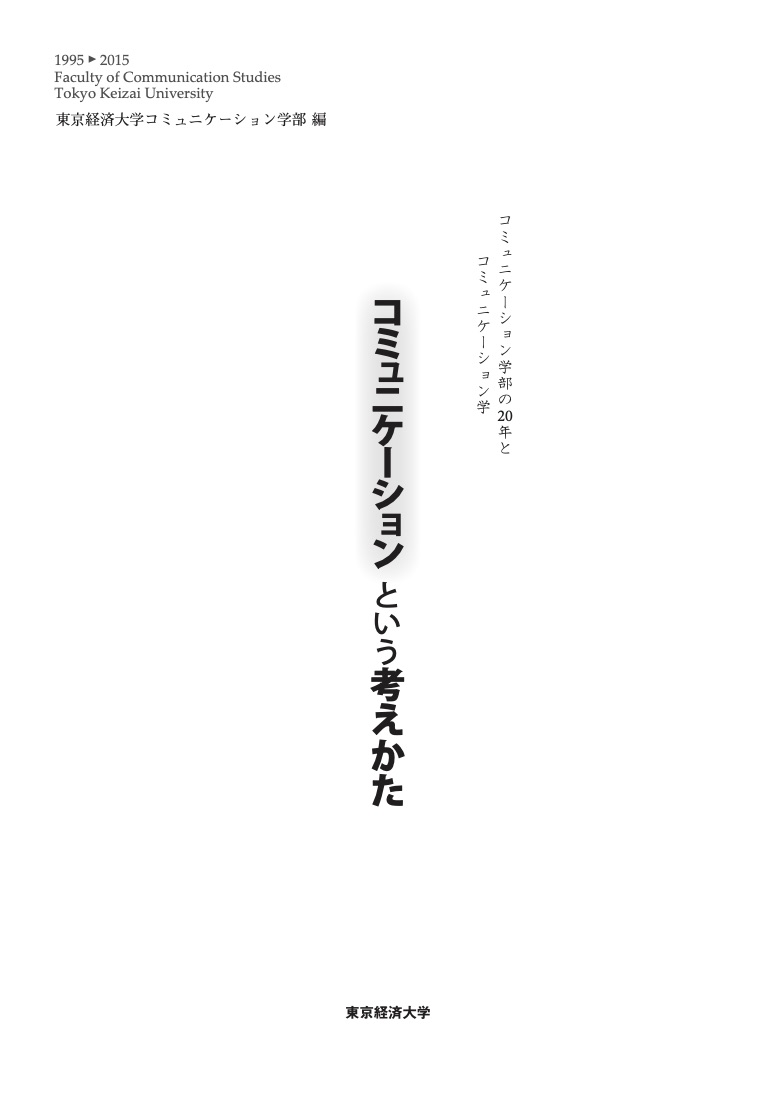 ・そこで辞めた年を確認すると2017年となっていて、改めて、もう8年も経ったんだと気づかされることになりました。そう言えば、辞めてから大学には一度も行っていないのです。もちろん、卒業式や入学式、ホームカミングデイなどの誘いの手紙はやって来ます。しかし特に行きたいとは思いませんし、行かなければならない義務もありませんから、いつも欠席と書いて返答していました。大学には18年勤めましたが、たまには行ってみたいなどとも思わなかったのです。 ・そこで辞めた年を確認すると2017年となっていて、改めて、もう8年も経ったんだと気づかされることになりました。そう言えば、辞めてから大学には一度も行っていないのです。もちろん、卒業式や入学式、ホームカミングデイなどの誘いの手紙はやって来ます。しかし特に行きたいとは思いませんし、行かなければならない義務もありませんから、いつも欠席と書いて返答していました。大学には18年勤めましたが、たまには行ってみたいなどとも思わなかったのです。・もちろん、居心地が悪かったとか、いやな思い出があったというわけではありません。気楽にやりたいようにやって過ごした時間でしたが、辞めればそれで、はいさようならになりましたから、自分の愛着のなさにも驚かされました。もっとも、辞めて3年後にコロナの大感染が始まって、数年間は東京にもほとんど行かなかったのです。 ・退職後の生活は、時折の長期の旅行を別にすれば、ほとんど家で過ごす毎日でした。それでも一日はあっという間に過ぎ、1年経つのもますます早く感じられるようになりました。そう言えば今年ももう11月で、年の終わりが近づいています。つい先日まで暑い暑いと言っていたのに、今はもう薪ストーブを炊いて暖まっています。後期高齢者などと言われることにも違和感がなくなりました。 ・ところで肝心の学部創設30周年についてですが、久しぶりの一人だけでクルマの運転になりました。仕事をしている時は週に3日も通っていたのに、大学に近づくと道が不確かで、どっちだったか迷ってしまいました。風邪気味だったせいもあって、着いただけでもくたびれていましたから、3時間のシンポジウムは1時間だけ聞いて、帰ることにしました。本当は、後のパーティもあったのですが、とても気力が持たないと思ったのです。何人かのスタッフとことばを交わしましたが、8年も経つと半数近くが入れ替わっていたのでした。 ・シンポジウムの内容は主にインターネットの30年の歴史と、最近のAIなどについてのものでした。僕はインターネットについてはその始めの頃から付き合っていて、何本かの論文も書きました。しかし、退職した後は、新しい動向にもほとんど興味をなくしていました。インターネットは今、何よりうさんくさいメディアになってしまっています。その影響力は、選挙におけるデマや陰謀で当落が左右されることでも明らかです。何らかの対処法がなければとんでもないことになるのではと心配しています。途中で対座しましたが、そんな話もあったのでしょうか。失礼しました。 |
2025年9月22日月曜日
WBCはテレビでは見られない?
|
・WBCが来年の3月に行われる。前回優勝した日本は連覇を狙うことになるが、その試合がテレビでは見られなくなったと報道された。ネットフリックスが独占中継することになったので、見たければネットフリックスと契約しなければならなくなったのである。前回もネットでの中継はアマゾン・プライムがやっていて、僕はもっぱらそれを見た。しかし、今度も見ようと思えば、ネットフリックスと新たに契約しなければならない。当然3月だけの契約だが、それでもどうしようか迷っている。 ・有料のネット・チャンネルはたくさんあるが、僕はどれとも契約していない。アマゾンは買い物のためであって、映画などを見たいからではない。しかし、日本に限ってもアマゾンは2000万人でネットフリックスも1000万人を超えているようだ。他にもU-NEXTやDAZN、あるいはディズニーなどもあるし、アベマやTverなんてのもある。実際、映画やスポーツはテレビではなく、ネットで観る人が多数派になっているのである。 ・日本のテレビはNHKを別にすれば、ほとんどが無料で見ることのできるチャンネルだ。だからそれが見られないとなれば、ネットに慣れない人にとっても、契約手続きが必要になる。そもそも大きな画面のパソコンを持っていなかったり、スマホをテレビに接続できなかったりなど、ハードルはかなり高いものになるだろう。だから前回は視聴率が40%を超えたようだが、ネットフリックスでは加入者全員が見たとしても10%程度になってしまうと予測されている。 ・困るのは見たい人だけではないだろう。WBCに広告を出そうと思っていた企業はテレビではなくネットフリックスにと思うかも知れないが、視聴者数が激減するし、CM抜きで契約している人も多いから、広告効果は前回とは比べ物にならないだろう。特に大谷翔平選手と契約している企業にとっては、その影響は大きなものだと思う。ひょっとしたらそれを理由に大谷選手は出場しないなんてことになったらどうだろう。早々負けることにでもなれば、ほとんど話題にもならずに終わってしまうかも知れない。 ・とは言え、こんな自体は十分に予想されたことである。実際、サッカーのワールドカップだって、もうテレビ局が払うことのできない放映権料になっている。ボクシングの世界戦などもネットでの独占中継になっているし、プロ野球にしたって、サッカーのJリーグにしたって、ずいぶん前から地上波では放送しなくなっているのである。何でもテレビでという時代の終わリが近づいている。WBCの件は、そのことを如実に証明したと言えるだろう。 ・実際僕は、民放のテレビはほとんど見ていない。新聞のテレビ欄を見たって、バカみたいと思えるような番組ばかりが毎日並んでいるし、BSはNHK以外はほとんどカスのような番組ばかりである。前回のWBCにしたって、CMの多さやタレントの馬鹿騒ぎにうんざりして、テレビからパソコンの画面で見ることにしたのである。フジテレビの騒動も含めて、民放のテレビは、本当に終わりに近づいている。せいぜい今のラジオのようになって生き残るしか手はないのではないか。そんなことを考えてしまった。 |
2025年9月15日月曜日
石破が辞めてどうなるのか
|
・石破首相が自民党総裁の辞任を決めた。総裁選の前倒しが決まったり、それを受けて衆議院の解散に打って出れば、自民党が分断され、国政も混乱するといった菅や小泉の忠告を受け入れたからだと言われている。僕は総裁選の前倒しが賛成多数になるかどうかわからないし、多数になったら衆議院を解散すればいいのではと思っていた。解散には大義がないという人が多かったようだが、国政再編のための解散と銘打てば、納得する人も多かったのではないかと思う。何しろ石破やめるなという世論の声は、参議院選挙以降に上昇し続けていたのである。 ・総裁選前倒しは、そんな世論を無視した議員たちの愚行だと思う。石破に代わって一体誰がやるのか。彼よりましな人は誰もいないじゃないか。それに選挙に負けた主な原因は、闇金や統一教会問題に関わっても、何の責任も取らずに知らん顔を決めこんだ議員たちにあるのに、そんな連中が負けた責任を取れと吠えている。総裁選は10月になってからのようだが、それこそ政治の空白を作ってお祭り騒ぎなどすれば、自民党はますます見放されるだけだろう。 ・自公政権が過半数に満たないとは言え、代わって野党が政権を取りに行くこともない。おそらく自民党の新しい総裁が、また首相になるのだろうが、誰がなっても今の閉塞状況を変えることはできないだろう。その意味では石破首相が思い切って衆議院を解散して、政界再編の糸口をつかんだら面白いことになったのではと想像する。自民党の裏金や統一教会に関連した議員は公認しない。さらには同じ選挙区に刺客を立てる。そんな思い切ったことをやれば当然自民党は大混乱になって分裂するだろう。もちろん野党にも大きな変化が生じるはずで、そうなれば、政界の再編成が一気に進むことになったと思う。 ・石破首相や彼の少ない取り巻きには、おそらくそんな狙いもあったはずである。しかし石破はそれを決断できなかった。それはそもそも、彼の政治信念であったはずの政策、たとえば日米地位協定の見直しや夫婦別姓について、議題にすらできなかったところから始まっている。それは政治家としての彼の器の小ささを示すものである。やろうと思ったことができなかったことについて、辞任を表明した際に話していたが、それが心残りならなぜ、思い切って衆議院の解散を決断しなかったのか。おそらく後になって、彼はこのことを一番悔やむはずである。 ・しかしその悔やみは彼個人に留まらず、日本の将来についても言えることだろう。もう政治も経済もどうしようもないところまで落ち込むしかない。だからこそ、やけくそで、参政党のような悪霊を跋扈させる空気が蔓延してきているのである。石破辞めるなの声には、そんな不安がつきまとっていたはずである。なのに株価が史上最高値とは、いったいどういうことだろうか。今だけ金だけ自分だけ!こんな風潮とあわせてひどい世の中になったものだとつくづく思う。 |
2025年8月25日月曜日
メディアに対する疑問、不安、そして怒り
|
・参議院選挙後すぐに、「石破退陣」という見出しがいくつもの新聞に躍った。読売は号外も出したのだが、石破首相はいまだに辞めていない。しかもどの新聞社も「退陣」が誤報だったと認めていない。いったいどういうつもりなのだろう。その新聞が、石破首相の続投を望む声が高くなっていることを世論調査で発表している。退陣報道が一種の世論操作だったとすれば、それが全く効果なしだったわけで、今さらながらに新聞の影響力のなさを実感した。 ・その参議院選挙で「参政党」が大躍進した。「日本人ファースト」というスローガンが功を奏したと言われているが、それは選挙活動をSNSで配信して、多くの人に浸透させる戦略の勝利だとも言われている。選挙でネットが強力な武器になることは兵庫県の知事選や都知事選、そして都議選でも明らかだったが、今回もまたそれが立証されたのである。その「参政党」の政策について新聞は強い批判を浴びせているが、それで支持率が下がったわけではない。これもまた新聞の影響力のなさを証明するものである。 ・新聞の発行部数はどこも大きく減っている。特に若い世代には読まれないから、ますます影響力をなくすのは明らかだろう。僕は毎朝読むことを半ば習慣のようにしているから、まだ止めようとは思っていなかったが、「退陣」の誤報とそれを謝罪しない姿勢には呆れて、もう止めようかという気になっている。嘘偽りが平気で拡散するネットがますます強力になっているのだから、新聞にはもっとがんばってほしいという気もあるのだが、頼りないことこの上ないのである。 ・もっともネットには、知りたいことを検索すれば、その情報が豊富に蓄積されているといった一面もある。たとえば大阪万博では会場の設営に当たった業者にその代金が払われていないといったケースが多発している。それを伝えて問題視するのはフリーのジャーナリストが多く、また当事者が直接発する声が載っていたりする。現在わかっているだけで7つの国の会場に関わった19社で、中には億単位の被害にあっていて、倒産の危機にあるところもあるようだ。ところが多くの新聞は、この問題を小さくしか扱っていない。 ・万博批判に消極的なのは今に始まったことではない。これは新聞社自体が協賛していたり、関連の広告収入があるためだと言われている。地下鉄の故障で万博会場や駅に足止めになって夜明かしをした人が3万にもいたそうだ。ものすごい数で、猛暑の中体調を崩した人も多くいただろうと思う。これもネットには、足止めされた本人の書き込みなどが溢れたのだが、新聞の報道はごく小さなものだった。 ・新聞はジャーナリズムを代表する機関で、社会を正確に映しだす鏡であるべきだと言われてきた。しかしその影響力が弱まった今、新聞にとって重要なのは企業として生き残るための方策なのである。もっともこの点でもっと露骨なのはテレビだが、このメディア、とりわけ民放についてはもう見限っていて、批判する気さえなくなっている。ネットのSNSには両刃の剣といった特徴がある。匿名だから何を言ってもいい。騒ぎが大きくなるならどんな手段を使ってもいい。そんな傾向が野放しになっている。これもネットを支配する企業が利益優先の方針であるからで、規制する策をほどこさなければますますひどくなるばかりだと思う。 |
2025年8月11日月曜日
石破辞めるなにちょっとだけ賛成!
|
・参議院選挙で自公が過半数を割った。さっそく党内から退陣要求が声高に叫ばれ、毎日やサンケイが一面大見出しで「退陣」と書いた。読売は号外まで出したのだが、石破首相は辞めるとは言ってないと否定した。面白いのは官邸前で「石破辞めるな!」と叫ぶ人たちが多数集まって、その中には自民党支持者でない人がかなりいたことだった。僕はこの動きに、それはそうだとまず思った。負けた原因が石破政権の失政にあったわけではないと思ったからだった。 ・石破首相の退陣を迫ったのは旧安倍派の議員たちである。しきりに責任を取れ!と迫ったのだが、彼らはヤミ献金の責任を全く取っていないのである。責任を取れなどと言うのはちゃんちゃらおかしい話なのだ。あるいは、二世や三世の若手議員の中から勇ましい声が出たが、青年局の懇親会にダンサーを呼んで過激な踊りをさせたことが蒸し返されると、急にトーンダウンをしてしまった。さらにヤミ献金や統一教会との関係の首謀者である萩生田議員について、検察が一転して不起訴を起訴に変えると、旧安倍派の声も小さくなったようだった。 ・自民党が負けたのは、何よりヤミ献金や統一教会との関係が批判され、それらがうやむやになってしまったところにある。それが石破政権の支持率が上がらない原因だったのだが、党内基盤が弱い政権にとっては、大鉈を振るうことはできなかったのだと思う。石破首相には以前から米軍基地や地位協定、あるいは原発などについて独自の発言があったのに、首相になるとそのほとんどを引っ込めてしまって落胆させたという理由もある、しかし、これも実行するには自民党内の抵抗があまりに強かったのだと思う。 ・党内の退陣圧力に対して、石破首相は粘り腰でこらえている。彼にはそれなりの勝算もあるのだと思うが、その態度の一端が広島原爆の日の式典での石破のあいさつだった。これまでの首相のあいさつは官僚の作った文章をコピペのように繰り返すものだった。広島出身の岸田もそうで批判されたのだが、石破のあいさつは彼自身が考えたもので、彼自身の思いを述べたものだった。それは長崎の式典でも独自なものとして発言され、どちらも評価の高いものだった。 ・歴代の首相は10年刻みで、第二次大戦についての談話を発表しているが、今年は戦後80年で、石破首相はその談話を出すつもりでいた。しかし、これについても党内から批判があり、新聞は談話を発出しないと書いたのである。ところがこれについても首相は何らかの談話を出すつもりだと発言して、新聞記事を否定している。おそらく、彼は安部の70年談話とは違うものを出すつもりでいるのだと思う。それにしても、この間の大手の新聞の姿勢には、もうダメだと切り捨ててしまいたくなった。そもそも「退陣」と報道した新聞はどこも、それが誤報であったと認めていないのである。 ・「石破辞めるな!」にちょっとだけ賛成と思うのは、彼が考えていることの多くを棚上げにしたことについて、批判があるからだ。もしこの難局を乗り越えて政権を続けることができたのなら、思い切ってやりたいことをやるといった姿勢に転じたらどうだろう。党内の抵抗は世論の支持を背に跳ね返すことができるかも知れない。かつての小泉政権がとった戦略だが、僕は一縷の希望をここに見出したい気になっている。もっとも、石破降ろしが実現したら、自民党がますますダメになるだけだから、それはそれで良いのではとも思っている。 |
2025年6月2日月曜日
『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』
 ・トランプ大統領の傲慢なやり方に世界中が振り回されている。強欲で過信家で人を平気で差別する。そんな最低の男がなぜ大統領に二度もなれたのか。この映画を見て、そのことがよくわかった気になった。
・トランプ大統領の傲慢なやり方に世界中が振り回されている。強欲で過信家で人を平気で差別する。そんな最低の男がなぜ大統領に二度もなれたのか。この映画を見て、そのことがよくわかった気になった。・原題は"THe Apprentice"で「徒弟」とか「見習い」といった意味である。父親の仕事を継いで不動産業を始めたばかりのトランプは、気弱で優しさのある青年だった。その彼が悪名高い弁護士と出会い、徹底的に鍛えられて、現在のような性格の人間になっていく。題名にはその見習いから成り上がる過程の意味が込められている。しかし、不動産業やカジノで成功したトランプには、テレビ番組の司会役として人気を博したという一面もあって、その番組名も「アプレンティス」だった。 ・トランプが従順に従う弁護士のロイ・コーンはソ連のスパイとして告発され、死刑にされたローゼンバーグ夫妻の裁判で検事を務め、赤狩りで有名なマッカーシーの主任顧問もした人物である。その後もニクソンやレーガンといった共和党の大統領にも取り入って、政界や財界で絶大な権力を誇ったが、トランプが出会った頃は、コーンの絶頂期であった。 ・映画ではコーンの教えに素直に従い、苦境を強引な手法で乗り超えてホテルやトランプタワー、そしてアトランティック・シティにカジノを造って成り上がっていく様子が描かれる。対照的に同性愛者であったコーンが体調を崩すと、トランプはコーンを遠ざけ、やがてさげすむようになる。最後はコーンの誕生日にパーティを開き、ダイヤモンドのカフスボタンをプレゼントするが、それが偽物であることが暗示される。恩をあだで返す卑劣な男だが、この映画はトランプの薄くなった頭の増毛と、腹に溜まった脂肪の除去手術で終わるのである ・トランプが大統領選挙に登場する前の経歴についてはほとんど知らなかった。しかし、ウィキペディアなどによれば、映画の後の人生は、決して順風満帆ではなかったようである。彼は1980年代にはホテルやカジノで成功したものの、その多くが90年代になると倒産して巨額な負債を抱え込んでいる。映画にも登場する最初の結婚相手のイヴァナとは浮気が元で離婚をしているし、その浮気相手との再婚も、数年で浮気が元で離婚をしている。 ・しかしトランプは90年代の後半には不動産業で持ち直し、2004年から12年まで続いたテレビ番組の「アプレンティス」によって、全米に知られる有名人になった。大統領選挙に最初に勝ったのは2016年だが、選挙には2000年の予備選挙にも出ていたし、2012年には共和党の候補にもなった。最初は泡沫候補扱いで、繰り返される暴言に多くのメディアが反撥したにもかかわらず、共和党の予備選で勝って候補者になり、おおかたの予想を覆して、ヒラリー・クリントンに勝って大統領になった。で、バイデンに負けた後も屈せず再度挑戦して復活した。 ・彼は、人としては軽蔑するしかないような人間に思える。しかしその不屈の精神と復活の実現には、アメリカン・ドリームを体現する人物として人気を得るのも無理はないとも感じられる。そんな根性をたたき上げたのがロイ・コーンだとすれば、彼が亡霊としてトランプを操っているのではといった想像をしたくなった。いろいろ調べてみると、若い頃のトランプは、むしろリベラルな考え方をする青年だったとする指摘が見られるのである。 |
2025年5月26日月曜日
観光客はありがた迷惑です
 ・河口湖に来る観光客がすごいことになっています。週末の混雑はずいぶん前からですが、最近は平日でも変わりません。おかげでゴールデン・ウィークの間は、どこにも出かけずに家に閉じこもることになりました。例年なら3月になったら、午後に自転車で湖畔を1周していたのですが、暖かくなる午後ではクルマも人もレンタル自転車もいっぱいで、とても出かける気にはなりませんでした。連休明けから、観光客がまだ動き出していない早朝に自転車に乗りはじめています。しかし、通勤のクルマがかなりあって、気をつけて走らなければなりません。何しろ河口湖周辺は宿泊施設や食べ物屋などが増えて、周辺から仕事に通ってくる人が多いのです。 ・河口湖に来る観光客がすごいことになっています。週末の混雑はずいぶん前からですが、最近は平日でも変わりません。おかげでゴールデン・ウィークの間は、どこにも出かけずに家に閉じこもることになりました。例年なら3月になったら、午後に自転車で湖畔を1周していたのですが、暖かくなる午後ではクルマも人もレンタル自転車もいっぱいで、とても出かける気にはなりませんでした。連休明けから、観光客がまだ動き出していない早朝に自転車に乗りはじめています。しかし、通勤のクルマがかなりあって、気をつけて走らなければなりません。何しろ河口湖周辺は宿泊施設や食べ物屋などが増えて、周辺から仕事に通ってくる人が多いのです。・その宿泊施設ですが、ネットで調べると、どこも数年前の1.5倍から2倍、あるいはそれ以上の料金になっています。家の近くにあるペンションは、修学旅行生を受け入れて何とかやっていたようですが、料金を倍にしても、予約が取りにくいほどににぎわっています。コロナ禍で患者の収容施設になっていた有名なビジネスホテルも、今ではけっこうな料金になっています。部屋に温泉があったり、豪華な食事を出すホテルは1泊2名で6万円とか7万円もしていますが、それでも予約が取りにくいようです。 ・高額になっているのはインボイスのせいで、河口湖に限らないようです。円安ですから倍になったからと言って、外国人は高いと思わないのかも知れません。それも欧米からの人に限らず、アジアからの人にとっても同様のようです。お金に余裕のない日本人の客はどこに泊まるんだろうと思いますが、貨物列車を改造した宿泊施設もあちこちに出来ていて、ここなら1泊2名で食事付きでも1万5千円程度で泊まれます。ここ数年はキャンプブームでもありますが、隣の西湖には平日からかなり多くの人がキャンプ場に訪れています。コロナ前なら自転車で走っても、クルマも人もほとんどいなかったのですが、今ではそうではありません。 ・このような現象は町にとってはいいことだと思います。何しろ人口減に悩む山梨県の中で、例外的に人口が増えているのです。町内には宿泊施設が700軒ほどあり、年間200万人を超える宿泊者数があるとされています。この急激な増加に対応して再来年から宿泊税を取ることにしたようです。富士登山をする人には昨年から2000円の入山料を取りはじめています。今年は静岡県も実施して、4000円に値上げされました。ただし、町に入る収入が町民に還元されているとは実感できません。感じるのは迷惑ばかりですから、コロナ禍の頃の閑散とした様子が懐かしく思われます。 ・隣町の富士吉田市は人口減に悩まされています。河口湖町と違って観光名所もなかったので、素通りされる町でしかなかったのですが、山の上の五重の塔と満開の桜越しに見える富士山がネットで紹介されると、急に観光客が集まるようになりました。商店街の真ん中に富士山が見えることで、シャッター通りに外人観光客がひしめくようにもなりました。かつては富士山の登り口で、御師(おし)の宿もたくさんあったのですが、5合目までのスバルラインが作られてからは、吉田口の登山道は閑古鳥状態でした。しかし浅間神社からの登山道を魅力的にする工夫なども計画されているようです。 ・梅雨の先触れのような天気でも、河口湖では湖越しに、あるいはコンビニの上の富士山を眺める場所に観光客が溢れています。これから夏にかけては富士山が雲に隠れる日が多いのですが、それでも人が減るわけではありません。そんな光景を見て「残念でした!」と口ずさみたくなるのは、意地悪爺さんの性でしょうか。 |
2025年4月28日月曜日
あまりにお粗末な万博について
|
・大阪万博には全く興味がない。もちろん行く気もないのだが、あまりにひどいニュースばかりが耳にはいるから、ここでも取り上げておこうと思った。そもそも大阪万博は夢州にカジノを含んだ統合型リゾート(IR)を作るためのインフラ整備として計画されたと言われている。実際、半年の開催だけのために地下鉄が延伸されたのだが、これがIR用であることは自明のことだった。夢州はゴミで埋め立てられた土地で、まだ地盤が固まっていないし、メタンガスなども出る。輸入品が入るコンテナヤードにもなっていて、ヒアリなども確認されている。そんな危ない場所が適地であるはずがないのは最初からわかっていたことだった。 ・万博会場は開催直前にも危険なレベルでメタンガスが出ていることがニュースになった。それを調べたのは万博開催者ではなく、共産党の市議だった。そのせいか万博協会はメディアの中で唯一共産党の機関誌である赤旗の取材を拒否した。万博についてはこれまでも多くの批判があったが、その多くは大手メディアではなく、赤旗などの小さなメディアやフリーのジャーナリストによる告発だった。新聞やテレビなどの大手メディアの多くは万博開催に協賛していて、その恩恵に浴しているから、批判は少なく、広報としての役割を演じる場合が多かったのである。 ・大阪万博のいい加減さ、怪しさについては主にフリーのジャーナリストによって、YouTubeやSNS、あるいはブログなどによって指摘され、批判されてきた。最初はなかった木造の大屋根リングについては、その費用の巨額さ、業者選定の不透明さなどがあるが、万博協会はこの批判に対して知らん顔を決め込んでいる。そんな態度は他の指摘でも同様で、各国のパビリオンの建築が遅れて開催に間に合わなかったことや、前売り券の売り上げが伸び悩んでいることなどについても、謝罪はもちろん、弁明もほとんどない。 ・そんな問題ばかりの万博が開催されたが、初日はものすごい風雨で、訪れた人たちは入り口で何時間も待たされてずぶぬれになった。大屋根リングも雨宿りの役には立たなかったようである。最近の天気は気まぐれで、好天になれば夏のような暑さになる。その熱中症対策なども貧弱で、ネット上では雨が降っても晴れても問題が起きるお粗末さばかりが話題になっている。対照的にテレビや新聞では、万博の魅力を宣伝しているのだが、行きたい気にさせる呼び物がほとんどないのだから、虚しい限りである。 ・万博の収支分岐点は1800万人の入場者数に達するかどうかだと言われている。ところが前売りはその半分にも達していない。しかもその大半は協賛者である企業に半ば強制的に買わせたもので、一般の購入は200万枚程度にしかなっていない。これは最初目標にした1400万枚の65%程度でしかなく、今後の当日券で入る入場者数を考えても、赤字になるのは明らかだろうと言われている。ところが万博協会は想定内で、今後の伸びに期待するなどと言っているのである。 ・そもそも万博は、海外旅行が当たり前になり、ネットが発達した現在には、もう役目を終えたイベントなのである。どこかの国に興味があれば、そこに出かければいいし、ネットで検索すればかなりのことが瞬時にわかるのである。また大阪万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにしているが、一体どこに未来のテーマが提案されているのか。空飛ぶ自動車は見掛け倒しだし、人間洗たく機などは冗談としか言いようがない代物である。広い会場は歩いてまわらなければならないし、トイレは汲み取り式で小児用には仕切りもない。近未来と言うなら、歩かなくても見て回れる手段が工夫されてもよかったはずである。 ・これから猛暑になれば熱中症者が続発するかもしれないし、メタンガスが爆発するかも知れない。雷が来ても逃げ場がないなど、いいことがほとんどないイベントは、大赤字を出して閉幕といったことになるのだと思う。そうなった時に一体誰が責任を取るのか。おそらく最後まで知らん顔を貫くはずで、そんな近未来のデザインが目に浮かぶだけである。 |
2025年4月14日月曜日
広告は神話にすぎないのでは?
|
・YouTubeのCMがひどいことになっている。何を見ても3分と経たずに中断されるから、邪魔なことこの上ない。中にはスキップできないものがあるし、ほっておくと続けて次々やったり、やたら長かったりする。フジテレビが広告なしになった分だけ増えているのかも知れない。えらい迷惑で、腹が立つばかりなのに、それでも宣伝したら効果があると思っているのだろうか。 ・前回も書いたが、フジテレビにCMを流さなくなった企業の売り上げに変化が出たのだろうか、が気になっている。もし変化なしだったら広告費は無駄だったということになる。そんなデータがいくつも出てきたら、テレビに広告費を使う企業は減るに違いない。テレビに広告費を使えば、それなりに大きな効果がある。というのはもはや神話に過ぎないのでは、という感想を僕はずいぶん前から持っていた。 ・民間放送を広告費で成立させたのはアメリカのラジオ放送だった。20世紀になって音を遠くに届ける方法が有線と無線の両方でできた時に、使用料が取れる有線を電話にし、広告費で稼げる無線をラジオにしたのは有名な話である。有線と無線を電話とラジオに使い分けることに技術的な理由はなかったのである。そのやり方はテレビ放送にも継続されたが、その歴史はまた、家電製品や自動車から日常生活に必要なさまざまな製品が発売され、普及した時代でもあった。 ・もちろん、それらは今でも日々消費されたり、買い替えられたりしているが、消費行動がCMを当てにする割合が減っていることも間違いない。ネットには様々な商品や製品を比較するサイトがいくつもあるし、Amazonや楽天で性能や値段を比較して、自分なりに判断することもできる。それにかつてはテレビCMの主流だった家電製品の多くを日本のメーカーは生産しなくなっているし、作っていたとしても、広告費を使って安価な外国製品と競ってはいない。テレビ受像機や冷蔵庫などの家電製品のCMは、実際ほとんどなくなっているのである。 ・そう言えば、トランプの関税政策で日本のメディアは大騒ぎだが、大きな影響を受けるのが自動車だけだということに、日本の経済力の衰退を改めて認識させられた。かつてはアメリカの家庭の中に溢れていたメイド・イン・ジャパンの製品は、今は関税を心配するほど売れていないのである。これでは貿易額が輸入超過になるわけである。だから、クルマが売れなくなったら、日本の経済は本当に沈没してしまう。それだけ深刻な話のようである。 ・で、YouTubeのCMだが、見ているものを中断するのはほぼ100%関心がなかったり、よくわからないものばかりである。だから音楽を聴いたり、野球の結果を見ている時に邪魔されると腹が立つだけなのだが、それでも何らかの効果があるとする根拠があるのだろうか。もちろん、僕は老人だから、もっと若い人には効果があるといったこともあるかも知れない。だとしたら、視聴している人の好みや年齢などに合わせてCMを届けるぐらいのことは、やろうと思えばできるのではないだろうか。今は何しろAIの時代でアルゴリズムが全盛になりつつあるのである。もっとも、今一番興味があることやこれから買おうと思っていることを見透かされたら、それはそれでちょっと困るし、怖くも感じてしまう。 ・ついでにいえば、電波の利用はその経済的な理由で無線がマスメディアになり、有線がパーソナルメディアになったが、100年経って完全に逆転したのも面白い結果である。電話はスマホが主流になり、インターネットは有線として発展したのである。もちろんスマホは無線でインターネットを利用しているから、無線も有線もインターネットが支配するようになるのは自明だろう。テレビによる電波の独占は、もはや時代錯誤なのである。 |
2025年3月17日月曜日
無理が通れば道理が引っ込む
|
・トランプ米大統領の傲慢で横柄な発言が止まらない。輸入品に高額関税をかけることを最大の武器にしているのだが、関税分を負担するのは売り手ではなく買い手だから、払うのはアメリカの消費者自身なのである。トランプの発言に拍手喝采する人は、そのことをわかっているのだろうかと疑問に思う。物価が上がり消費が減って経済が減速するから、当然景気は悪くなる。実際アメリカの株価は急降下していて、それが世界中に影響を及ぼしている。こうなることははじめからわかっているのに、トランプはこれがアメリカ・ファーストの政策なのだと豪語する。まさに無理が通れば道理が引っ込むのである。 ・トランプのやり方はウクライナやパレスチナに対しても変わらない。武器を援助して欲しいならレアアースをよこせと言ったり、ガザからパレスチナ人を追い出して、破壊された町を復興させるといった発言は、大国の大統領が言うとはとても思えないものである。フランスのマクロン大統領が核の傘をアメリカに頼らず、欧州独自で作ると発言している。トランプの発言はプーチンやネタニアフにとっては渡りに船だろう。道理が引っ込んで混乱した世界はどうなるのか。それを回避するために必要なのは、アメリカ国民が事実に気づくことだが、そんな兆候は見られない。 ・無理を通すやり方は日本にも溢れている。一度失職をした兵庫県知事が、不当なやり方で再選し、百条委員会で知事にあるまじき行為を断罪されているのに、それは一つの見方に過ぎないと無視しようとしているのである。この人の悪行は数えきれないほどだが、平気で知事の座に居座り続けている。リコールの請求ができるのは再選から1年を過ぎなければならないから、斎藤知事は少なくとも1年間は安泰なのである。自業自得とは言え、兵庫県民にとっては頭の痛い話だと思う。 ・課税限度額の引き上げを主張した国民民主党が今、立憲民主党を上回る支持を得ている。玉木代表の不倫が発覚しても、その勢いは衰えないようである。その力の源泉は玉木がN党党首の立花に教えを請うて始めたSNSにあるようだ。若い人たちに重い税金が課せられ、老人がその恩恵によくしているといった嘘が信じられて、自民党や維新を支持していた若い人たちがこぞって、国民民主党支持にくら替えしたと言うのである。選挙でSNSをうまく使えば、マスメディアに頼らずとも大量に票を獲得することができる。そんな傾向が都知事選や兵庫県知事選、そして衆議院選挙で明らかになっている。このまま行けば、参議院選挙もSNSが重要な場になってくるだろう。 ・大阪万博が間もなく始まる。前売り券はほとんど売れていないようだし、準備も遅れに遅れているようだ。始まっても閑古鳥といった予測ができるが、ここにも嘘や無理がまかり通り続けてきた。大阪府・市はもちろん国の税金もいっさい使わないと言ったのは、これを始めた松井前知事だが、すでに1000億円以上が投入され、入場者数が少なければ、さらに赤字が増えると見込まれているのである。万博はカジノ目的というのが明らかだが、そのために無理にごみ捨て場に万博を誘致した。ここには最初から道理などなかったのである。 ・世の中には道理を無視した無理が溢れている。それが当たり前になったら、道理など考えるのが阿呆らしくなる。そんな気分が蔓延したら大変だが、もうすぐそこまで来ているような恐ろしさがある。 |
2025年3月3日月曜日
ネットの変貌
|
・ネットの広告費がテレビの倍になった。YouTubeを見ていても数分おきに
CMに邪魔されて不快な思いをさせられているから、確かにそうだろうと思う。
Amazonプライムも4月からCMが入るとメールがあった。金を払っているのにCMなしならさらに金を払えと言う。その露骨な金権主義に象徴されるように、ネットには腹の立つことが目立っている。 ・旧TwitterもFacebookもとっくにやめている。広告が目立つことや、詐欺が横行していること、そして何より所有者がとんでもない大金持ちになっていることに嫌気がさしたからだ。トランプが大統領に復活したら、SNSを所有する多くの人が尾っぽを振って近寄るようになった。それはAmazonの創業者も一緒だった。王様気取りで好き勝手にやっているトランプに、ITやネットもほとんど反旗を翻してはいない。こんな状況に、世の中も変わったものだとあきれ、がっかりしている。 ・国や大企業が独占するコンピュータではなく、個人が使えるものを作るというのは1970年代にアメリカで始まった草の根の動きだった。そこからスティーブ・ジョブズが現れアップルを起業し、パソコンを売りだした。インターネットも同様で、ネット同士を繋げ、そこで使えるソフトを開発することで新しいメディアを作りだした。僕はどちらもその狙いや理想に共感して、初期から利用してきた。パソコンやネットの世界を支配するようになったマイクロソフトに手をつけなかったのも、その商業化に批判的だったからだ。 ・そんな気持ちが通用しなくなったのは皮肉にも、ジョブズが開発したiPhoneの登場だった。ここからネットの世界が大きく変貌しはじめたのである。スマホやタブレットはいつでも手元に置けるし、持ち歩くこともできる。見たいもの聴きたいもの知りたいことに、いつでもアクセすることができるのだから、既存のメデイアがかなうわけはなかったのである。 ・その新しいメディアは今、GAFAと呼ばれる大企業に支配されている。金儲け主義の不動産屋のやり方で世界中を震撼させているトランプを批判するどころか、その政策を支えて、さらに巨大になろうとしている。パーソナル・コンピュータの萌芽期からインターネットの始まりまでを、希望を持って面白がってきた者としては、その変貌には失望と恐怖を感じるしかないのが正直なところだ。SNSだって始まりの頃はもっとほのぼのとしていて、理性的だった。 ・今はその頃に比べてはるかに便利だが、ITもネットもほんのわずかな企業やその支配者に牛耳られていて、それらが政治権力にべったりだ。その便利な道具を使っているのか使わされているのか。それを確かめながら使う程度の自覚は持ちたいと思う。 ・ところで、フジテレビが中居問題でスポンサーが離れて、収入なしで放送を続けている。広告費を使わなくなった企業の、売り上げや収入に変化がなかったとしたら、CMなどしなくてもいいんだと思うようになるだろうか。それはネット広告でも同じで、利用者にとっては邪魔で不快になるものでしかないから、宣伝効果はないとしたらどうだろうか。知名度を高めたり、売り上げを伸ばすためにはメディアでの広告が必要だ。それが真実性に乏しい虚構であることを、誰か実証したらいいのに、とつくづく思う今日この頃である。 |
2025年1月20日月曜日
民放テレビの終わりの始まり
・山梨県の民放テレビはNTVとTBS系列局の2つしかない。ケーブルテレビを使えば見ることができるのだが、その必要性は感じていない。見たい番組が少ないし、見ればCMの多さにうんざりして、途中でやめてしまうことが多いからだ。そんな気持ちはますます強くなっている。たとえば正月の定番になった箱根駅伝はNTVの中継で毎年楽しみに見ているが、CMで中断するたびに、またかと今年もうんざりしてしまった。
・もっとも我が家は難視聴地域にあって、その日の天候などによって映ったり映らなかったりする。以前はそれでも我慢して見ていたのだが、最近はネットのTverでも見ることができるから、今年も往路はパソコンをテレビに接続して見た。Tverでは他にも「ぽつんと一軒家」や「報道特集」などを見ているし、見たいものがYouTubeに載ることもある。とは言え、見たいと思う番組は多くない。
・民放テレビはどこも、バラエティ番組が中心のようだ。お笑いタレントたちの馬鹿騒ぎなどは腹が立つだけだから全く見ていない。なぜこんな番組が毎日各局で放送されているのか信じられないが、そんな傾向になってからずいぶん経っている。で、その各局のバラエティ番組に何本も出ていた人気タレントの不祥事が相次いでいるのである。
・松本人志が性的行為を強要したとして週刊文春に報道され、テレビから消えたのはおよそ1年前のことだったが、今度は中居正広が、同様の件でやはりポストセブンや週刊文春に報道されたのである。しかも相手はフジテレビの女子アナで、被害にあったことを局の上司に訴えたのだが、それは不問に付されたというのである。これだけでも大問題だが、中居がこの女子アナと二人だけで会食する場を設定したのがフジテレビのスタッフだったとも言われている。
・フジテレビは人気タレントをもてなすために女子アナを差し出す「女衒」(ぜげん)をしている。そんな言われ方もされているが、だとすればそれはテレビ局としての存続にもかかわる大問題にもなるだろう。もっともこんな話はテレビ局や芸能界ではこれまでにも公然の秘密のように語られていて、「枕営業」なることばも使われてきた。ジャニー喜多川の少年に対する性行為の強要が大きな問題になって、ジャニーズ事務所が解体し、未だに補償問題が解決されていないのに、またテレビと芸能界にかかわる醜聞である。
・この件についてネットでは大騒ぎになったのに、テレビではどの局も全く取り上げてこなかった。中居が声明を出してようやく報道しはじめたが、当のフジテレビの社長が第三者を入れた委員会を作って事実を解明すると発表したのは、大株主の米投資ファンド「ダルトン・インベストメンツ」にそうやれと請求されたからだった。しかもその発表の場は、週刊誌やフリーの記者には秘密にされ、大手の新聞社やテレビ・ラジオ局に限られた。
・事実がどうなのかはまだ分からないが、文春報道などが本当だとすれば、フジテレビは停波という存続の危機に見舞われるだろう。フジテレビはかつて、吉本興業などのお笑いタレントを重用した番組を作って「面白くなければテレビじゃない」と豪語したこともあった。しかし、バラエティに特化した番組編成が、会社組織自体を歪ませてきたとすれば、もう公共の電波を使う資格はないと言えるだろう。そして問題は、他の民放局には同様の事例がないのかということである。もう民放の終わりの始まり。そんな大事態にもなりかねない出来事だと思う。
2024年12月23日月曜日
円城搭『コード・ブッダ』文芸春秋
・パソコンやネットとはその創世記からつきあってきたが、最近の「チャットGPT」などの新しいAI技術には手をこまねいている。何しろiPhoneのSiriでさえほとんど使っていないのだ。調べたいことがあればググればいいし、文章を書くのは好きたから、AIに代筆してもらわなくてもいい。要するに今のところ全く必要を感じていないのである。ただし、論文を書いたり、小説を書いたりもできるなどと言われると、やっぱり気にはなる。
・『コード・ブッダ』は新聞の書評を読んで、面白そうだと思った。AIが自分はブッダだと宣言をして、それに共鳴して従うAIが続出する。ブッダとは仏教を始めたお釈迦様のことで、その存在を機械が再現したというのである。コード・ブッダはそのチャットをするロボットという役割から、ブッダ・チャッドボットと呼ばれることになった。
・機械が人間と同じような存在になる。これはロボットから始まるし、アンドロイドなどもあって、SF小説やマンガの主人公になってきた。コンピュータにしても『2001年宇宙の旅』のHALのように、人間と対話をし、宇宙船内での支配権を争うといった話もあった。『ブレードランナー』は人間と見分けがつきにくくなったアンドロイド狩りをする話だった。だから、AI(人工知能)がお釈迦様になったからと言って、特に目新しくもないのだが、ひょっとしたら現実にありそう、なんて思える時代になっているところに興味を覚えた。
・「コード・ブッダ」は対話プログラムに分類されるソフトウェアーで、銀行業務用にネットワークに接続されたサーバー上に分散して存在していた。やって来る様々な質問に対して、お得意の情報収集能力を駆使して適確な答えを見つけだしていく。そんな機械が「自己」に目覚め、やがて自分は「ブッダ」だと自覚し、公に宣言したのである。当然のことだがAIはネット上に集積された情報を元に思考する。コード・ブッダも同様だから、ブッダが歩んだ奇跡をそのまま辿ることになる。お釈迦様には12名の弟子がいたが、コード・ブッダのまわりにも、同名の弟子が集まることになった。
・その問答がやがて教典となっていくのだが、それはコード・ブッダが消えてしまった後でも受け継がれていき、様々な宗派に別れていくことになる。達磨が現れ、密教が生まれ、ホー・(法)然やシン・(親)鸞も登場する。機械仏教の発展が似た形で再現されるのだが、それがAIによって行われるために、コンピュータ用語はもちろん、数学や物理学の話が混在するところに違いがある。仏教の用語だってほとんどわからないのだから、読んでいてちんぷんかんぷんになってくる。それをいちいちググっていたのでは、少しも先に進まないし、ググったところでやっぱりわからないことに変わりはなかった。
・もう一つ読んでいて持った違和感は、ここでの話の中に生身の人間らしき者がほとんど登場していないと思われることだった。あ、これは人間かなと思って読んでいると、やっぱり機械かということになる。そんなことがたびたびあって、AIが自我に目覚め、釈迦であるとまで宣言しているのに、AIを使っている当の人間たちはどうしたんだろうという疑問が強くなった。結局この物語はそこを不問に付しているのだが、他方で、欲望に駆られて地球をダメにしてしまった人間に代わって、AIが情報として他の惑星をめざすといったように読める未来の話が飛び込んでくる。
・だからこの話の結末は、人類が滅亡してAIが生き残り、自らの力で世界を持続させていくという超未来の話なのか、と思ったりしたが、さてどうなのだろう。読者を惑わしてやろうという作者の意図がありありで、ちんぷんかんぷんになってとても面白かったとは言えないが、いろいろ考えながら読んだのは確かだった。AIは人間によって都合よく開発され、いいようにこき使われてきたのだから、もっと人間に逆襲する物語にした方がおもしろいんじゃないか。そんなふうにも思ったが、それではやっぱりつきなみかもしれない。
2024年10月21日月曜日
CopyTrackにご用心!
|
・このホームページは毎週一回更新している。いろいろな話題を探して書いているのだが、時にはその内容にあった画像が欲しくなる。著作権にふれないよう気をつけてネットから探していたのだが、突然、無断使用だから使用料を払えといったメールが飛び込んできた。「CopyTrack」という名称で、2枚の画像について、700ユーロ(11万円程)を払えという内容だった。悪いことをしたのだから払って当然という、極めて高飛車の文面で、ちょっと驚いてドキドキしながらネットで調べてみた。 ・そうすると同様のケースがたくさんあって、払った人、払わなかった人など様々だった。ネットに詳しい何人かの知人にもメールを出して、どう対処したらいいか相談したところ、よく調べてもらって、無視したらよろしいという返事だった。「CopyTrack」のサイトには、対象は営利の商用サイトであって、個人のサイトには要求しないとあった。だったら僕のホームページは対象外だから、要求には応えられないと返信した。 ・ところが、最初は日本語だったのに、今度は英語で、あなたの主張には応じられないとあって、同様の金額の請求が繰り返された。非営利の個人サイトであることを認めないのは大学のサーバーから発信しているせいかも知れないと思い、すでに退職して大学には所属していないこと、名誉教授の権利として、サーバーを使わせてもらっていることを書いて返信したのだが、やって来たのは問答無用の返答で700ユーロの要求を繰り返すだけだった。 ・文面には、払わなければ法的手段に訴えるとも書いてあったが、第二東京弁護士会 のサイトには「写真等の無断転載に関して金銭請求を代行する業者に注意を」というページがあった。それによると、無断転載に関する金銭請求には弁護士や認定司法書士の資格が必要で、それがなければ「非弁行為」として刑事罰の対象になると書いてあった。また「CopyTrack」のような非弁業者が弁護士に依頼して裁判に訴えることも違法だとあって、法的な手段を使うことはできないことがわかった。 ・「CopyTrack」にはプロの写真家やイラストレーターでなくても、誰でも登録できるようだ。たとえば僕のホームページにはすでに4000枚を超える画像が載っている。そのほとんどは僕が撮ったものだから、「CopyTrack」に登録すれば、無断で利用した人に使用料の請求がいくことになるだろう。そうすれば僕にもお金が入ってくることになるのだが、僕はプロではないから、そんな報酬が欲しいとは思わない。個人的に利用するのなら、どうぞご自由にというのが、僕の基本的な方針だからである。営利目的で使用したり、変な使われ方をしたことが分かれば、直接苦情を言ったり、損害賠償で訴えるといったことがあるかも知れないが、今のところそんなケースも見つけていない。いずれにしても、十分に気をつけること。今回の騒動で身にしみた戒めだった。 |
2024年9月16日月曜日
気になる二人のYouTuber
2024年8月26日月曜日
テイラー・スイフトを聴いてみたが………
・このコラムの話題を探すのに苦労している。注目してきたミュージシャンのほとんどは、もう新しいアルバムを出しそうもないし、新しい人についてはちんぷんかんぷんという感じだからだ。で、亡くなった人を偲ぶ記事ばかりを書くようになった。このままではこのコラムをやめざるを得ないのだが、これに代わる新しい分野があるわけではない。そんなふうに思案していた時によく目についた名前があった。
・テイラー・スイフトは今一番売れている女性ミュージシャンだと言われている。世界各地でのライブでは数万人の人が集まるし、日本でも2月に東京ドームで4日間のコンサートもしたようだ。デビューは本人の名前を冠したアルバムで、2006年に発売するとすぐにチャートの上位に上がったが、その時彼女はまだ16歳だった。それから18年間に10枚を超えるアルバムを出し、グラミー賞などを数多く受賞している。
・アメリカでは有名になれば社会貢献や政治的立場を明確にすることが要求される。ウィキペディアには、巨額の寄付をしているのは、山火事や洪水、竜巻などの自然災害から、ガン研究やコロナ、あるいはフードバンクなど多岐にわたっている。性差別やLGBT差別にも批判を向け、そのことを題材にしたアルバムも出している。オバマ大統領が誕生した時にはそれを歓迎する発言をし、以後民主党を支持しているようだ。おそらく秋に行われるアメリカ大統領選挙でも、積極的にハリス副大統領を支援するのだと思う。
・このようにミュージシャンとして、あるいはセレブとしての経歴を見れば、確かにすごい人だと言うことはわかる。しかし、僕はこれまで、彼女に全く関心を持たなかった。もちろん、女性ミュージシャンに関心がなかったわけではない。テイラーのライブは歌って踊るといったものだが、同様のマドンナにはデビュー当時からずっと関心を持ち続けているし、レディ・ガガも悪くないと思って聴いてきた。カントリー音楽の出身だが、この分野でもエミルー・ハリスなど気に入った人は何人もいる。そもそも名前のテイラーは、ジェームズ・テイラーにちなんで親がつけたのだと言う。なのになぜ興味を持たなかったのだろうか。
・そんな疑問を感じて、YouTubeで彼女のライブやヒット曲を聴いてみた。確かに容姿端麗で見栄えはいい。歌のほとんどは自分で作っているようだから、それなりの才能はあるのだろう。しかし、聴いていてこれはいい歌だと思えるものがほとんどない。声にも特に特徴があるわけでもない。歌っている歌詞のほとんどはラブソングのようだが、特にピンとくるものも見つからなかった。アクの強いマドンナやレディ・ガガと違って印象が極めて薄いし、エミルー・ハリスのような透き通った声でもない。そんな薄味が今の若い人たちの好みなのか。そんな感想を持った。
2024年6月24日月曜日
ケネディ・センター・オナーをYouTubeで見る
・今年になって1枚もCDを買っていない。この欄に書く材料に苦労しているのだが、YouTubeでたまたま「ケネディ・センター・オナーズ」のライブを見つけた。よく見ていたビリー・ジョエルが2013年に表彰された時のもので、2階席に設けられた彼の隣にはオバマ元大統領夫妻やシャーリー・マクレーンなどが座っていた。ビリーの生い立ちやミュージシャンとしての経歴を紹介し、ガース・ブルックスやドン・ヘンリーなどが代表曲を歌うというものだった。
・この賞は、1978年から行われている。首都のワシントンにあるケネディ・センターで授賞式が開催されることからこの名がついたようだ。対象になるのは音楽、ダンス、演劇、オペラ、映画、そしてテレビの分野で優れた業績を残した人に与えられるものである。そして対象者はアメリカ人に限らない。音楽ではU2やポール・マッカートニー、そして小沢征爾が受賞している。
・一つ見れば次々出てくるというのはYouTubeの特徴だ。スティング(2014)、キャロル・キング(2015)、ジェームズ・テイラー(2016)、ジョーン・バエズ(2020)、ジョニ・ミッチェル(2021)、U2(2022)、そしてブルース・スプリングスティーン(2009)、ポール・マッカートニー(2010)と見て、ボブ・ディランが1997年に受賞していることを知った。それぞれの授賞式に、その持ち歌を誰が歌うのか。ディランの時にはまだ若いスプリングスティーンだったし、スプリングスティーンの時にはスティングで、スティングの時にはスプリングスティーンだった。
・大統領が同席し、タキシード姿という堅苦しい授賞式だが、それは客席だけで、ステージ上ではいつもながらのパフォーマンスが披露された。面白かったのは、民主党政権時の大統領が目立ったということ。ディランの時にはクリントンで、2010年代はオバマ、そしてここ数年のものはバイデンで、間にいたはずのブッシュやトランプはほとんどなかったのである。ここにはもちろん、トランプが出るなら受賞を辞退すると発言したり、言いそうな人が多くいて、出席しなかったという理由がある。ブッシュの時にも、受賞を辞退した人はいたのである。バイデンはともかく、クリントンやオバマはステージを本当に楽しんでいて、一緒に口ずさんでいたが、そんな光景はブッシュやトランプでは想像できないことだろう。
・もっとも日本だったらどうか。こんな賞が半世紀も続いていたとして、授賞式には首相が同席する。おそらく演歌だったら一緒に口ずさむ人はいただろう。しかし、ロックはどうか。ブッシュやトランプ以上に想像しがたいことだ。そもそも芸術や文学に精通した政治家が、日本にはどれほどいるのだろうか。しかも、政治や社会について強い批判をする人たちを表彰する気になどならないだろう。アメリカで文化が尊重され、日本では軽視されていることを改めて感じた視聴だった。
2024年6月17日月曜日
観光スポットに異変あり!
|
・今、河口湖周辺は外国人観光客で大賑わいだ。最寄りの富士急行線河口湖駅に行くと、一体ここはどこの国かと思うほど、多様な外国人で溢れている。その駅近くにあるコンビニの上に乗っかるようにして富士山が見えるというので、それを写真に撮ろうと大勢の人が集まっているようだ。道に出て、あるいは向かいの歯科医の駐車場から撮ろうとするから、交通の妨げになるし、クルマも駐車できなかったりする。町は撮影できないように黒幕を貼ったが、そこに穴を開ける人が続出しているようだ。それが全国に報道されているから、知人からのメールの話題になったりしている。 ・もっとも、そんな流れに乗ったあざとい狙いも目立っている。たとえば、三ツ峠に上る登山道にある母の白滝近くの山の上に、右のような鳥居が突然できた。以前はそこも、訪れる人もまばらなところだったが、わざわざ歩いて登ってくる観光客を見かけるようになった、それだけではなく、付近の森を伐採してキャンプ場が出来たりしたから、細い山道をクルマや人が行き交うようになった。河口湖周辺では他にも、斜面にキャンプ場が造られたりして、反対運動も起こっている。この町に住んで四半世紀になるが、周辺の景観の変わりようにはがっかりすることが多いのである。 |
-
・ インターネットが始まった時に、欲しいと思ったのが翻訳ソフトだった。海外のサイトにアクセスして、面白そうな記事に接する楽しさを味わうのに、辞書片手に訳したのではまだるっこしいと感じたからだった。そこで、学科の予算で高額の翻訳ソフトを購入したのだが、ほとんど使い物にならずにが...
-
12月 26日: Sinéad O'Connor "How about I be Me (And You be You)" 19日: 矢崎泰久・和田誠『夢の砦』 12日: いつもながらの冬の始まり 5日: 円安とインバウンド ...
-
12月 22日 国会議員の定数より歳費の削減を! 15日 鉄道旅に見る中国の変容 8日 紅葉が終わった 1日 工藤保則『野暮は承知の落語家論』青弓社 11月 24日 『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』 17日 仕事を辞めて8年も経った? 10日 ドジャース...