 |
・野菜はほぼ終わったが、サツマイモはまだ葉っぱが枯れていないので、収穫はもうちょっと後にしようと思っている。あちこちに種を蒔いたコスモスは、やっぱり日当たりがよいところが茎も花も大きくなった。来年は一番日当たりのいい丸太富士のまわりに蒔こうと思う。日当たりを求めるのは野菜も同じであることがよくわかったが、畑はさてどうするか。春までに新しい畑の場所を探さなければならない。 ・ところで彼岸までは猛烈に暑かったのに、10月になると秋らしいというよりは、もう冬かという日が何度かあった。それが夏のぶり返しのような日と交互にやって来るから、身体には良くないと思う。おまけに雨の日が多い。そんな冷たい雨が降る翌日に富士山が初冠雪の姿を現した。例年より3週間も遅いそうだが、去年よりは1ヶ月も早かった。
・ところで彼岸までは猛烈に暑かったのに、10月になると秋らしいというよりは、もう冬かという日が何度かあった。それが夏のぶり返しのような日と交互にやって来るから、身体には良くないと思う。おまけに雨の日が多い。そんな冷たい雨が降る翌日に富士山が初冠雪の姿を現した。例年より3週間も遅いそうだが、去年よりは1ヶ月も早かった。 ・そんなわけで、灯油を買いに出かけた。18Lを6缶で108Lだが、これでは空にしたファンヒーターと工房の床暖、それに給湯に入れたらお終いで、続けてもう一回買うことになった。寒い日にはアラジンストーブをつけ、夜はファンヒーターをセーブ運転にしている。これでまあまあ温かいが、最低気温が零度近くまで下がったら、薪ストーブも燃やそうと思っている。去年よりは一ヶ月も早いが、ちょっと前までは10月の後半には燃やしはじめていた。暑い日が長くなって、すぐに寒くなるのでは、秋がますます短くなってしまう。
・そんなわけで、灯油を買いに出かけた。18Lを6缶で108Lだが、これでは空にしたファンヒーターと工房の床暖、それに給湯に入れたらお終いで、続けてもう一回買うことになった。寒い日にはアラジンストーブをつけ、夜はファンヒーターをセーブ運転にしている。これでまあまあ温かいが、最低気温が零度近くまで下がったら、薪ストーブも燃やそうと思っている。去年よりは一ヶ月も早いが、ちょっと前までは10月の後半には燃やしはじめていた。暑い日が長くなって、すぐに寒くなるのでは、秋がますます短くなってしまう。 ・それは生き物にも言えるのだろうか。秋口になって屋根の軒に蜂が巣を作りはじめて、あっという間にご覧のような大きなものになった。ところが寒くなったら、しきりに飛び交っていた蜂が見えなくなった。春からならともかく、こんな時期に一体何のために巣作りをしたのだろうか。最近の気候変動は生き物にとっても予測しがたいものなのかもしれない。
・それは生き物にも言えるのだろうか。秋口になって屋根の軒に蜂が巣を作りはじめて、あっという間にご覧のような大きなものになった。ところが寒くなったら、しきりに飛び交っていた蜂が見えなくなった。春からならともかく、こんな時期に一体何のために巣作りをしたのだろうか。最近の気候変動は生き物にとっても予測しがたいものなのかもしれない。・天気が悪くて、しかも急に寒くなったから、自転車になかなか乗れなくなった。午後には暖かくなるのだが、レンタル自転車が多いし、クルマもかなり走っている。紅葉が本格化すれば大渋滞になるわけだから、厚着して朝早くでなければ走れないかも知れない。そんなわけで、かなり運動不足の今日この頃である。
|

 ・一昨年は上高地に行ったので、今回は乗鞍に行くことにした。道はマイカー禁止でバスで行くのだが、乗り場には上の畳平は濃霧で強風とあった。乗客は僕らともう二人だけ。行っても何も見えないとは言え、ひょっとしたら急に霧が晴れるかもと期待して、行くことにした。しかし、徐々に霧が濃くなり、畳平は雨が降って風も強く、とても歩ける状況ではなかった。仕方なく待合所にいてすぐにバスで下山した。
・一昨年は上高地に行ったので、今回は乗鞍に行くことにした。道はマイカー禁止でバスで行くのだが、乗り場には上の畳平は濃霧で強風とあった。乗客は僕らともう二人だけ。行っても何も見えないとは言え、ひょっとしたら急に霧が晴れるかもと期待して、行くことにした。しかし、徐々に霧が濃くなり、畳平は雨が降って風も強く、とても歩ける状況ではなかった。仕方なく待合所にいてすぐにバスで下山した。





 ・帰りはいつものように八ケ岳の農場に寄って野菜を買った。まさに収穫を感謝するかのように、大小のカボチャが並んでいた。それにしても上高地から松本に行く158号線はいつ走っても怖い。暗くて狭いトンネルでのバスとのすれ違いなどヒヤヒヤものだ。何しろバスやダンプはセンターラインをはみ出して来るのである。そんなわけで、久しぶりの長距離運転は心底くたびれた。
・帰りはいつものように八ケ岳の農場に寄って野菜を買った。まさに収穫を感謝するかのように、大小のカボチャが並んでいた。それにしても上高地から松本に行く158号線はいつ走っても怖い。暗くて狭いトンネルでのバスとのすれ違いなどヒヤヒヤものだ。何しろバスやダンプはセンターラインをはみ出して来るのである。そんなわけで、久しぶりの長距離運転は心底くたびれた。
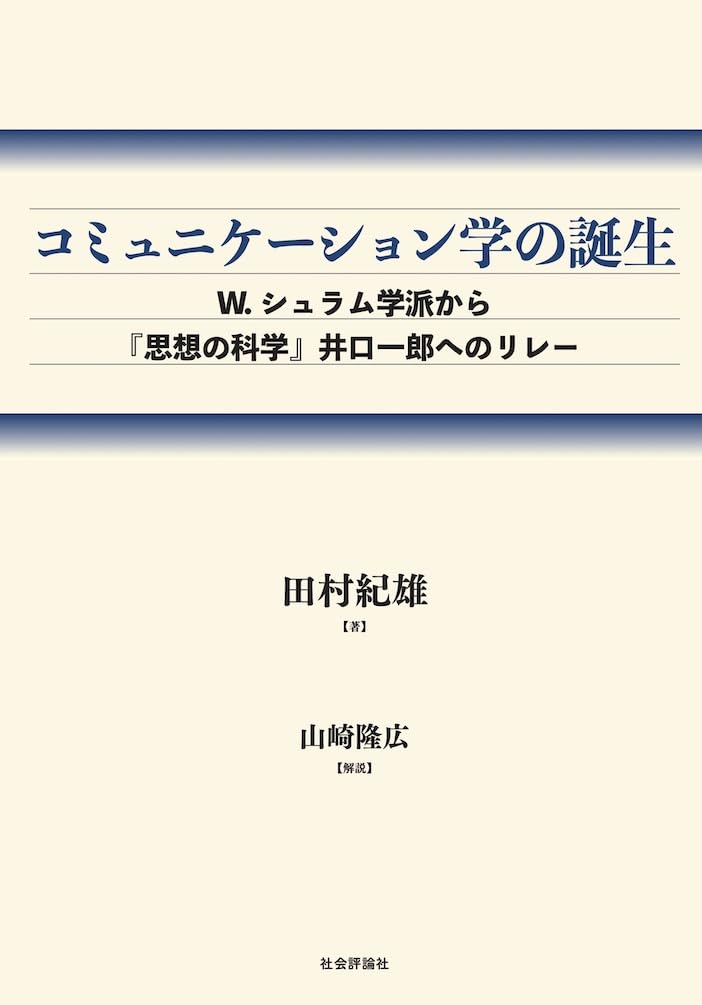 ・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。
・田村紀雄さんから今年も著書が届いた。もう90歳を超えているのにまだ研究生活を続けている。退職と同時に辞めてしまった僕とは雲泥の差である。せめてこの欄で紹介ぐらいはしなければいけない。そんなふうに思ってからもう何冊目になるのだろうか。三冊、四冊、五冊?いやいや恐縮するばかりである。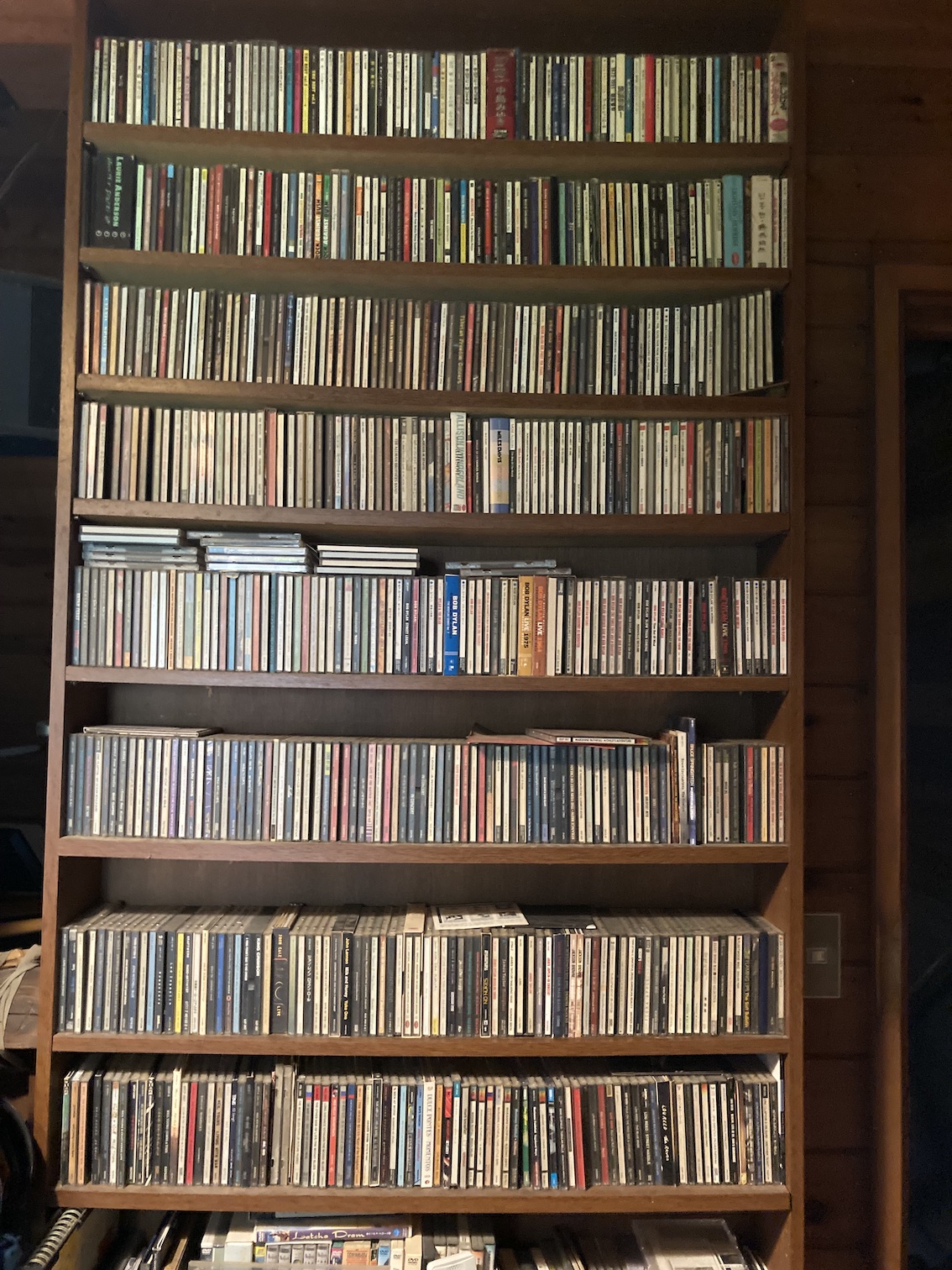 ・CDを買わなくなってもうずいぶんになる。と言ってダウンロードしているわけでもない。要するに、聴きたい音楽がほとんどなくなったのである。これまで良く聴いてきたミュージシャンの中には、亡くなってしまった人がかなりいるし、引退同然の人も多い。それに新しい人を探してなどといった気持ちもなくなっている。だからこのコラムに書くこともなくて困っているのである。
・CDを買わなくなってもうずいぶんになる。と言ってダウンロードしているわけでもない。要するに、聴きたい音楽がほとんどなくなったのである。これまで良く聴いてきたミュージシャンの中には、亡くなってしまった人がかなりいるし、引退同然の人も多い。それに新しい人を探してなどといった気持ちもなくなっている。だからこのコラムに書くこともなくて困っているのである。