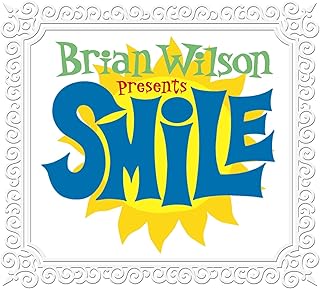 ・ブライアン・ウィルソンが亡くなったという記事を見つけて、そう言えば「スマイル」というアルバムを買ったな、と思い出した。ブライアン・ウィルソンはビーチボーイズのリーダーで、楽曲のほとんどを作っていた。1960年代の前半の頃で、陽気なサーフィン音楽で人気があった。僕はほとんど興味がなかったし、ボブ・ディランやビートルズに興味を持って以降、彼らの存在はほとんど忘れてしまっていた。
・ブライアン・ウィルソンが亡くなったという記事を見つけて、そう言えば「スマイル」というアルバムを買ったな、と思い出した。ブライアン・ウィルソンはビーチボーイズのリーダーで、楽曲のほとんどを作っていた。1960年代の前半の頃で、陽気なサーフィン音楽で人気があった。僕はほとんど興味がなかったし、ボブ・ディランやビートルズに興味を持って以降、彼らの存在はほとんど忘れてしまっていた。
・「スマイル」は2004年に発表されている。ビーチボーイズには何の興味もなかったのに、なぜこのCDを買ったのか。多分この作品とブライアン・ウィルソンをテーマにしたドキュメントを見たからだと記憶している。もともとこのアルバムはビーチボーイズとして1967年に発売される予定だった。それが未発表になったのは、ブライアンが思うようなサウンドに仕上げることができず、精神的に悪化して完成させることができなかったからだ。
・サーフィン音楽でヒット曲を連発していたビーチボーイズに転機が訪れたのはビートルズの出現だった。その新鮮なサウンドに刺激を受けたブライアンは、それに負けない新しいサウンドを作りたいと思った。それは音を重ね合わせる「ペットサウンド」としてビーチボーイズに新しい側面をもたらしたが、それで必ずしも人気が増したわけではなかった。今までと同じものを作ってほしいというレコード会社の要求に逆らって、ブライアンの作り出す音楽はますます複雑なものになっていった。
・それはロックンロールがロックになり、アルバムがヒット曲の寄せ集めではなく、1つのテーマを持った作品として見なされるようになった60年代後半の音楽状況にはあっていたが、ブライアンの周囲の人たちとは相いれない部分が多かったようだ。うまく作品ができないことと、バンドのメンバーや周囲の人たちとの軋轢などがあって、彼の心は壊れていったのだった。
・「スマイル」はそこから40年近くたって完成した。もちろん、収録されているのはブライアン一人で歌ったものである。その中には「グッド・ヴァイブレーション」のように、ビーチボーイズとして60年代後半にヒットした曲もある。ビーチボーイズ自体はメンバーの変更や分裂などにもかかわらずブライアンの死まで続いていたようだ。彼の死によって改めて探すとアマゾン・プライムに「ブライアン・ウィルソン ソングライター
ザ・ビーチ・ボーイズの光と影」というドキュメントがあった。2012年に作られたもので、3時間を超える長編だが、ブライアン・ウィルソンが歩いた、起伏の大きな歩みがよくわかった。
2025年7月14日月曜日
ブライアン・ウィルソンについて
2025年7月7日月曜日
加湿と除湿
 ・真冬に零下10度ぐらいまでになる我が家では、11月の末から4月の初めぐらいまで薪ストーブを炊いています。この季節は当然湿度も下がりますが、家の中を20度前後に暖めるとその分、強力に加湿する必要が出てきます。40~50%を維持しようと思えば、ストーブの上にいくつも鍋ややかんを乗せる必要がありますし、これ以外に加湿器を3台置いてほぼフル稼働にしなければなりません。外と中の寒暖差は大きい時で30度にもなりますが、湿度の差も30%以上になるのです。 ・真冬に零下10度ぐらいまでになる我が家では、11月の末から4月の初めぐらいまで薪ストーブを炊いています。この季節は当然湿度も下がりますが、家の中を20度前後に暖めるとその分、強力に加湿する必要が出てきます。40~50%を維持しようと思えば、ストーブの上にいくつも鍋ややかんを乗せる必要がありますし、これ以外に加湿器を3台置いてほぼフル稼働にしなければなりません。外と中の寒暖差は大きい時で30度にもなりますが、湿度の差も30%以上になるのです。・その加湿器の1つが壊れて新しいものを買おうということになりました。なるべく強力で、しかも静かなものをと探しましたが、どうせなら除湿もできるものはないかと思うようになりました。我が家にはエアコンはもちろん、数年前まで扇風機もありませんでした。真夏に30度を超えることなどめったになくて、その必要性を感じなかったのです。ところが暑さに我慢ができない日があって、扇風機を2台購入しました。それで何とか暑さをしのいできたのですが、年々暑さがひどくなって、そのうちエアコンが必要になるかもと思うようになりました。 ・我が家は松や欅の大木に覆われています。それで直射日光を避けて温度も低いのですが、その分湿気がたまります。毎年梅雨の季節になると家の中がかび臭くなって、何とかできないものかと思ってきました。エアコンをつければ除湿もやりますが、それは30度超えが当たり前になってからの話です。そこで加湿と除湿が強力にできる機種を探すことにしました。いくつかあって音が小さくて強力だという製品を購入することにしました。別売のフィルターなどと合わせると14万円もする、思い切った買い物でした。  ・3月末に購入してしばらくは、その日の天気や湿度に合わせて加湿だったり除湿だったりしましたが、5月になると、せっせと除湿をするようになりました。梅雨の前触れで雨の日が続きましたが、湿度は60%前後で推移して、例年ならかび臭くなる時期になってもその気配がありませんでした。6月になると真夏のような温度になり、我が家でも30度を超える日が数日ありました。その時、天気予報を見て、湿度は温度の上昇とともに下がることに気づきました。そこで日中の数時間は窓を開放して風を入れることにして、夕方から朝にかけては窓を閉めて除湿器を使うことにしました。これで何とか60%台後半の湿度を保たせることができています。
・3月末に購入してしばらくは、その日の天気や湿度に合わせて加湿だったり除湿だったりしましたが、5月になると、せっせと除湿をするようになりました。梅雨の前触れで雨の日が続きましたが、湿度は60%前後で推移して、例年ならかび臭くなる時期になってもその気配がありませんでした。6月になると真夏のような温度になり、我が家でも30度を超える日が数日ありました。その時、天気予報を見て、湿度は温度の上昇とともに下がることに気づきました。そこで日中の数時間は窓を開放して風を入れることにして、夕方から朝にかけては窓を閉めて除湿器を使うことにしました。これで何とか60%台後半の湿度を保たせることができています。・マニュアルにはフル稼働で1日9リットルの除湿をするとありますが、タンクは3リットルですから8時間で満杯になるということになります。5~6時間置きに空にしますが、たまった量には驚くばかりです。まるで我が家に泉ができたように感じてしまいました。もっとも冬場はその何倍もの水をストーブの上に置いていますから、空気中にはかなりの水分があることはわかっていました。しかしそれでも、吸い取った水の量には改めて驚いてしまいました。 ・例年にない早い梅雨明けで、全国的には猛暑が続いています。おそらく我が家でも30度超えの日が当たり前になることでしょう。その暑さを除湿器で乗り越えることができるか。毎年悩まされていたカビを克服することができるか。それはまた、夏の終わりに報告することにします。もうひとつ、この機種には洗濯物を乾かす機能もあって、その威力は何度か試しましたが、早々と梅雨が明けたので、しばらくは使う必要がなくなりました。 |
2025年6月30日月曜日
大相撲について気になること
|
・豊昇竜に続いて大の里が横綱になって、大相撲が活況を呈している。照ノ富士一人だった4年間から、一気に二人ということになり、日本生まれの横綱が稀勢の里以来7年ぶりに誕生したのである。その大の里は幕下付け出しからわずか2年で最高位まで昇りつめている。すでに4度の優勝をしているから、白鵬以来の大横綱になるのではと期待されている。 ・そんな大相撲だが、他方で白鵬(宮城野親方)が相撲協会を退職して話題になっている。弟子の暴力問題で部屋が閉鎖され、その謹慎期間が1年経っても解除されないというのが理由だった。相撲協会のこの処置については厳しすぎるのではという批判も起こっていて、同じ理由で相撲協会をやめた貴乃花の件も合わせて話題になっている。 ・現在の理事長は横綱北勝海の八角親方で2015年からの長期政権である。その間に八百長問題があり、コロナ禍での無観客場所もあって、大きな難局を乗り越えてきたと評価されている。しかし大横綱で将来の理事長と目されていた貴乃花や、優勝回数や通算勝利数で歴代一位の白鵬を退職に追い込んだことで、その政治的な野心も批判されている。現在62歳だから65歳の定年まで理事長を務めるのではないかと言われているし、定年延長さえもくろんでいるといった批判も起きている。 ・そういった内実は僕には分からないが、そもそも彼が理事長になる前の千代の富士との間にも確執があったようだ。北の湖理事長のあとは当然千代の富士と言われていたのになぜ、弟弟子の北勝海だったのか。そこには千代の富士の傲慢さに対する協会理事たちの批判や不信があったようだ。北の湖理事長の急死で北勝海が理事長になり、まもなくして千代の富士も亡くなることになったのである。 ・もちろん、理事長になろうとする意欲は貴乃花にも白鵬にもあった。と言うよりありすぎたと言った方がいいかも知れない。そのために協会の理事たちの信頼を勝ち得ることはできなかったと言われている。それは大相撲の世界の旧態依然とした古さのせいだと言うこともできるだろう。とは言え、千代の富士が北の湖の後の理事長になり、その後を貴乃花が引き継いで現在に至っていたとしたらどうだろうか。もっと良くなっていたか、悪くなっていたかはわからない。 ・ところで、テレビ中継に解説者として出る親方たちが例外なく連発することばに「やっぱり」がある。気になって「うるさい」と言いたくなるほどだし、ほとんど例外なく誰もが使うから、親方同士はもちろん、親方と力士、そして力士同士の間でも良く使われているのだろうと思う。「やっぱり」は「やはり」から変化したもので、思った通りとか予測通りといった意味で、結局は同じ結果になるさまに使われることばである。このことばが相撲界で良く使われるということは、昔から言われてきた伝統の正しさやそれに従うことの当然視が骨の髄までたたき込まれているのでは、といった疑問を感じてしまう。 ・そう言えば解説者としての北の富士から、「やっぱり」を聞いた記憶はない。なろうと思えば理事長になれたかもしれなかったのに、親方も辞めて解説者になった。そんな旧態然とした相撲界とは距離をとった彼と、弟子だった八角理事長との関係はどうだったんだろう。そんなことも気になってきた。ともあれ大相撲は新しい時代になりつつある。華やかな土俵の裏に闇の世界があるとすれば、「やっぱり」ではなく、時代の変化に合わせて変えていってほしいと思う。 |
2025年6月23日月曜日
丸太富士と野鳥の巣箱
 |
・伐採した松の木を薪にした後に残った大木をどうするか(下左)。あれこれ考えて、富士山を作ってみることにした。一番細い木をまず、一人で起こせる110cmの長さに切って、その3本を中心に置き、後は細いものから太いものへ90cm、70cm、50cm、30cmと刻んで、まわりに並べていった。丸太の間はおがくずや皮で埋めて完成。早速パートナーが山登りをした。我が家の海抜は850mほどあるから、丸太富士の頂上は851mということになる。ほんのわずかだが、上に登ると景色が変わって見えるから不思議だ。
・野菜畑で順調なのはスナップエンドウだけで、これはもうおいしくいただいた(左上)。プチトマトやキュウリも花が咲いて小さな実がつきはじめているから、もう少ししたら食べられるかも知れない(右上)。アスパラガスは細いのが数本出てきたが、1年目はそのままにして根を育てた方がいいようだ(左下)。ジャガイモはひょろひょろと背丈が伸びてしまっている。調べると栄養過多とあった(右下)。アンデスの痩せた土地で育ったのだから、次から日当たりのいい所に肥料を入れない畑を作ろうと思う。
・先週紹介した『僕には鳥の言葉がわかる』に触発されて巣箱を二つ作って松と欅につけた。もう子育てが済んでいるから入らないと思うが、一度だけ覗きに来たのを見かけた。来年のためにもっと作ってみようか。シジュウカラの入り口は28mmとあった。他の野鳥のために、大きさもいろいろ変えてみようと思っている。
|
2025年6月16日月曜日
鈴木俊貴『僕には鳥の言葉がわかる』小学館
・森の中に住んでいるから、いろいろな野鳥の鳴き声が聞こえてくる。だんだんうまくなるウグイスのホーホケキョーやホトトギスのテッペンカケタカは楽しいが、身体の大きいヒヨドリや籠脱け鳥のガビチョウはやかましいだけだ。そんなふうに勝手に聞いているだけだったが、その泣き声に意味があって、鳥同士でコミュニケーションをしているという指摘には驚かされた。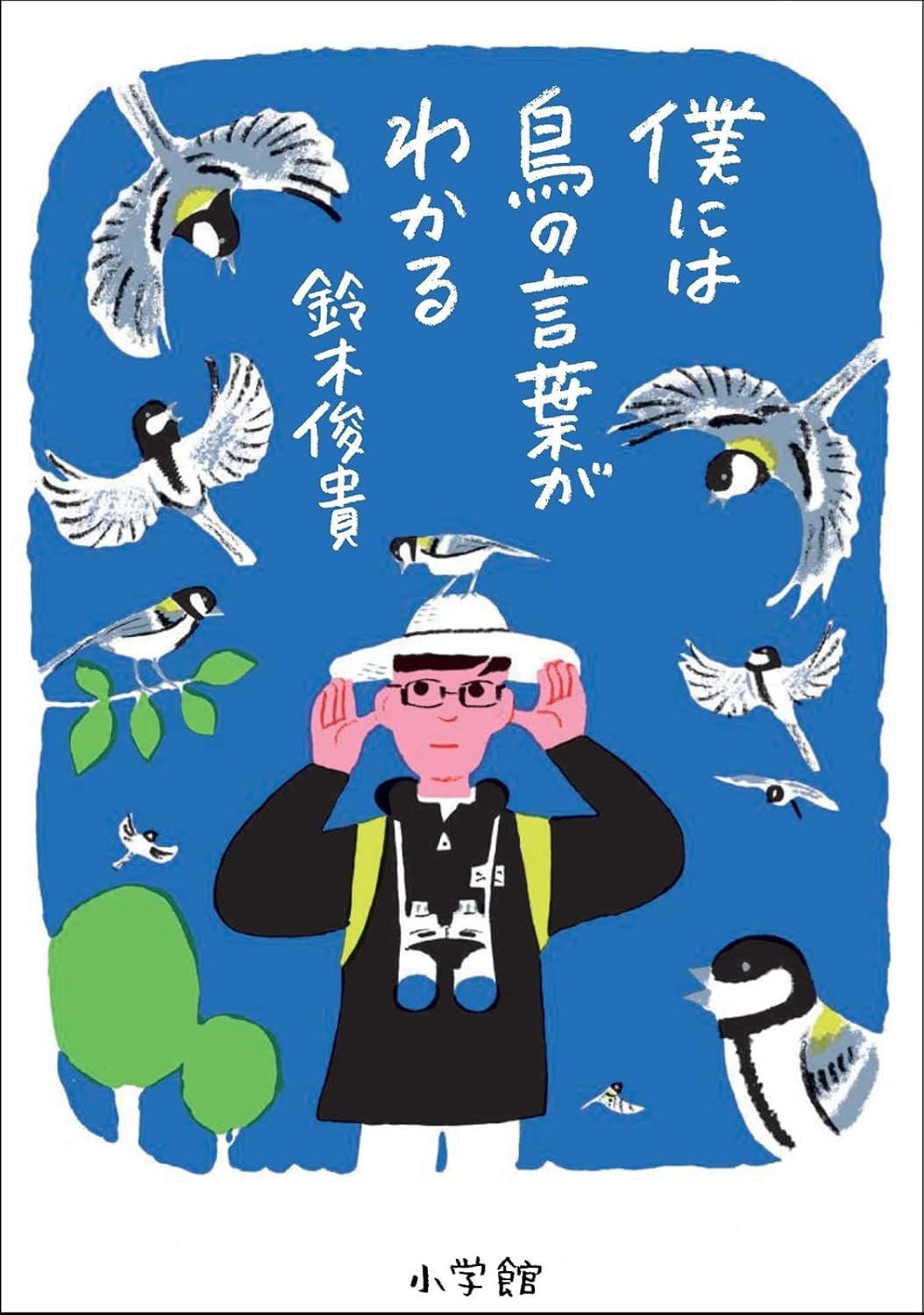 ・シジュウカラやヤマガラは我が家でもよく見かける野鳥である。その鳴き声は良く聴いていたのだが、それに意味があるとは思わなかった。ところがこの本によるとシジュウカラの「ピーツピ」には「警戒しろ」、「ヂヂヂヂ」には「集まれ」の意味があって、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」で「警戒して集まれ」になるという。何か餌になるものが大量にある時などに、仲間に知らせるために鳴くというのである。この鳴き方はもちろんタカやカラスなどが近づいた時にも使われるようだ。
・シジュウカラやヤマガラは我が家でもよく見かける野鳥である。その鳴き声は良く聴いていたのだが、それに意味があるとは思わなかった。ところがこの本によるとシジュウカラの「ピーツピ」には「警戒しろ」、「ヂヂヂヂ」には「集まれ」の意味があって、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」で「警戒して集まれ」になるという。何か餌になるものが大量にある時などに、仲間に知らせるために鳴くというのである。この鳴き方はもちろんタカやカラスなどが近づいた時にも使われるようだ。・著者の鈴木俊貴は現在では世界的に著名な動物言語学者で、シジュウカラの観察を20年ほど前の大学生の時から始めている。学部の卒論を書くために軽井沢にある大学の山荘に3ヶ月間滞在し、ヒマワリの種を置いてシジュウカラを集め、その鳴き声を記録し、その行動を観察したのである。その最初から「ピーツピ・ヂヂヂヂ」が「警戒して集まれ」になることはわかったのだが、それを実証するための観察が、その後大学院に進学し、博士論文を書き、動物行動学の雑誌に投稿する作業として十数年も繰り返されたのである。 ・多くの事例を得るためには巣箱をたくさん作り、毎年出かける必要がある。それは大変な作業だが、それを何より楽しんでやってきたことが、この本を読むとよくわかる。シジュウカラは街中でも良く見かける野鳥だが、それを見つける術もだんだんうまくなり、軽井沢に行かなくても観察できる機会が増えてくる。いやいや、ここまで来ると完璧なオタクだが、観察結果を逐次論文にして投稿し、それが次第に世界的な注目を集めるようになっていったのだから、読みながらもう感心するしかなかった。 ・しかもすごいのは、この研究の価値が単に野鳥の鳴き声の意味に限定されるものではないことだった。そもそもことばはギリシャのアリストテレス以来、人間しか話さないものだとされてきて、それは動物行動学においても自明の理だった。動物が鳴いたり吠えたりするのはことばになる以前の感情表現であって、そこには意味を伝える意図などはないとされてきたのである。著者はそこに疑問を呈して、シジュウカラがことばを使ってコミュニケーションをしていることを、豊富な観察記録から実証して見せたのである。 ・だから著者はその専門分野を「動物言語学」としているが、これは彼が命名し、最初に名乗った領域である。これが鳥類だけでなく、他の動物の研究にも応用されていく可能性があるはずだから、それがすごい発見であることは間違いない。そうであれば「動物言語学」が、日本でも盛んな霊長類研究などからなぜ生まれなかったのか不思議だが、「ことばを話すのは人間だけ」が邪魔をしたのだろう。もう一つ、この本がすごいのは、そんな最先端の研究なのに、ごく軽い読み物になっていることである。 |
2025年6月9日月曜日
プログレを聴きながら
・「プログレ」は1960年代末ぐらいに登場したロック音楽のジャンルで、僕はその最初の頃からよく聴いていた。一番は「ピンクフロイド」だが、他にも「キングクリムゾン」や「イエス」などのバンドがあって、特に前衛的なミュージシャンとしてはフランク・ザッパがいた。同時代に流行したポップアートやドラッグ・カルチャーと融合して、70年代から80年代にかけて隆盛を誇っていたが、90年代以降にはあまり聴かれなくなった。
・そのプログレが、今はYouTubeでライブやAIを駆使した動画とともに聴くことができる。僕はちょっと前からパソコンを使っている時によく聴いている。たとえばピンクフロイドの作品は、CDはもちろんレコードでもその大半を持っているが、聴くのはもっぱらYouTubeである。レコードはすでに聴きすぎて雑音ばかりだし、そもそもプレイヤーが壊れてしまっている。CDはというと、これも聴くことがほとんどないから、開けるとカビが目立って、きれいにしなければ聴けなかったりする。
 ・ピンクフロイドの代表作は「狂気」だが、「神秘」「原子心母」「アニマルズ」「ザ・ウォール」「炎」などのアルバムがあって、1983年の「ファイナル・カット」で解散ということになった。リーダーのロジャー・ウォーター抜きで、その後もいくつかのアルバムを出したが、作品のほとんどを作っていたロジャーぬきでは今一つという感じだった。もっともボーカルとギターを担っていたのはデヴィッド・ギルモアだったから、ヒット曲を演奏するライブには影響なく、僕はそのロジャー・ウォーター抜きのピンクフロイドのライブを1988年に大坂城ホールで聴いて堪能したことを覚えている。
・ピンクフロイドの代表作は「狂気」だが、「神秘」「原子心母」「アニマルズ」「ザ・ウォール」「炎」などのアルバムがあって、1983年の「ファイナル・カット」で解散ということになった。リーダーのロジャー・ウォーター抜きで、その後もいくつかのアルバムを出したが、作品のほとんどを作っていたロジャーぬきでは今一つという感じだった。もっともボーカルとギターを担っていたのはデヴィッド・ギルモアだったから、ヒット曲を演奏するライブには影響なく、僕はそのロジャー・ウォーター抜きのピンクフロイドのライブを1988年に大坂城ホールで聴いて堪能したことを覚えている。
・その後、キングクリムゾンやイエスのライブにも出かけたが、もうプログレの全盛期を過ぎていたこともあって、会場が小さかったにもかかわらず観客は少なかった。ただすべてのバンドに共通していて、音の良さはもちろん、照明や舞台の背景に映る画像なども楽しむことができたから、どのライブも満足した。
・そんなジャンルは今ではほとんど消滅しているが、音楽そのものは古くさくないと僕は思っている。だからフォークソングなどには懐かしさを感じても、プログレはそうではない。何かクラシック音楽を聴くような気持ちだと言ってもいいだろう。音に集中して瞑想するように聴いてもいいし、何かをやりながら背景音楽として聴いてもいい。あるいはクルマを運転しながらというのも悪くない。
・というわけで、ピンクフロイドを初めとしたプログレは、僕にとっては今でも良く聴く音楽になっている。パソコンで何か作業をしながら、クルマを運転しながら、自転車をこいで補聴器から、そして薪割りをしながらイヤホンでと、すっかり定番になっている。
2025年6月2日月曜日
『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』
 ・トランプ大統領の傲慢なやり方に世界中が振り回されている。強欲で過信家で人を平気で差別する。そんな最低の男がなぜ大統領に二度もなれたのか。この映画を見て、そのことがよくわかった気になった。
・トランプ大統領の傲慢なやり方に世界中が振り回されている。強欲で過信家で人を平気で差別する。そんな最低の男がなぜ大統領に二度もなれたのか。この映画を見て、そのことがよくわかった気になった。・原題は"THe Apprentice"で「徒弟」とか「見習い」といった意味である。父親の仕事を継いで不動産業を始めたばかりのトランプは、気弱で優しさのある青年だった。その彼が悪名高い弁護士と出会い、徹底的に鍛えられて、現在のような性格の人間になっていく。題名にはその見習いから成り上がる過程の意味が込められている。しかし、不動産業やカジノで成功したトランプには、テレビ番組の司会役として人気を博したという一面もあって、その番組名も「アプレンティス」だった。 ・トランプが従順に従う弁護士のロイ・コーンはソ連のスパイとして告発され、死刑にされたローゼンバーグ夫妻の裁判で検事を務め、赤狩りで有名なマッカーシーの主任顧問もした人物である。その後もニクソンやレーガンといった共和党の大統領にも取り入って、政界や財界で絶大な権力を誇ったが、トランプが出会った頃は、コーンの絶頂期であった。 ・映画ではコーンの教えに素直に従い、苦境を強引な手法で乗り超えてホテルやトランプタワー、そしてアトランティック・シティにカジノを造って成り上がっていく様子が描かれる。対照的に同性愛者であったコーンが体調を崩すと、トランプはコーンを遠ざけ、やがてさげすむようになる。最後はコーンの誕生日にパーティを開き、ダイヤモンドのカフスボタンをプレゼントするが、それが偽物であることが暗示される。恩をあだで返す卑劣な男だが、この映画はトランプの薄くなった頭の増毛と、腹に溜まった脂肪の除去手術で終わるのである ・トランプが大統領選挙に登場する前の経歴についてはほとんど知らなかった。しかし、ウィキペディアなどによれば、映画の後の人生は、決して順風満帆ではなかったようである。彼は1980年代にはホテルやカジノで成功したものの、その多くが90年代になると倒産して巨額な負債を抱え込んでいる。映画にも登場する最初の結婚相手のイヴァナとは浮気が元で離婚をしているし、その浮気相手との再婚も、数年で浮気が元で離婚をしている。 ・しかしトランプは90年代の後半には不動産業で持ち直し、2004年から12年まで続いたテレビ番組の「アプレンティス」によって、全米に知られる有名人になった。大統領選挙に最初に勝ったのは2016年だが、選挙には2000年の予備選挙にも出ていたし、2012年には共和党の候補にもなった。最初は泡沫候補扱いで、繰り返される暴言に多くのメディアが反撥したにもかかわらず、共和党の予備選で勝って候補者になり、おおかたの予想を覆して、ヒラリー・クリントンに勝って大統領になった。で、バイデンに負けた後も屈せず再度挑戦して復活した。 ・彼は、人としては軽蔑するしかないような人間に思える。しかしその不屈の精神と復活の実現には、アメリカン・ドリームを体現する人物として人気を得るのも無理はないとも感じられる。そんな根性をたたき上げたのがロイ・コーンだとすれば、彼が亡霊としてトランプを操っているのではといった想像をしたくなった。いろいろ調べてみると、若い頃のトランプは、むしろリベラルな考え方をする青年だったとする指摘が見られるのである。 |
-
・ インターネットが始まった時に、欲しいと思ったのが翻訳ソフトだった。海外のサイトにアクセスして、面白そうな記事に接する楽しさを味わうのに、辞書片手に訳したのではまだるっこしいと感じたからだった。そこで、学科の予算で高額の翻訳ソフトを購入したのだが、ほとんど使い物にならずにが...
-
12月 26日: Sinéad O'Connor "How about I be Me (And You be You)" 19日: 矢崎泰久・和田誠『夢の砦』 12日: いつもながらの冬の始まり 5日: 円安とインバウンド ...
-
・ 今年のエンジェルスは出だしから快調だった。昨年ほどというわけには行かないが、大谷もそれなりに投げ、また打った。それが5月の後半からおかしくなり14連敗ということになった。それまで機能していた勝ちパターンが崩れ、勝っていても逆転される、点を取ればそれ以上に取られる、投手が...









